「この話、なんか引っかかるけど、どこが怖いの?」
読書好きなら一度は体験したことがある、あのゾワッとする感覚。あなたが気づけなかったたった一つの違和感が、日常を崩壊させる。それが「意味が分かると怖い話」の醍醐味です。
当記事は、ネットに溢れる普通の意味怖とは一線を画す、「狂気の館」オリジナルのショートホラーを厳選してお届けします。
子供を笑顔にするピエロ、亡き祖母を想う母、親身になってくれる上司……。最も安全で安心できるはずの「善意」が、いつの間にか「誰かの狂気」にすり替わっている。そんな、背筋が凍るような10本の物語を集めました。
すべての物語は、<物語の裏側>と<論理的な真相>をセットで解説しています。
まずはあなたの直感で物語の違和感を見つけ出してみてください。もし分からなければ、下の【解説付き】エリアで、一緒に答え合わせをしましょう。
あなたがこの10話の真相を読み終える頃には、きっと「隣人の笑顔」や「当たり前の日常」が、これまでと同じようには見えなくなっているはずです。
さあ、あなたの日常の安全は、どこまで侵食されているでしょうか?
『意味が分かると怖い話』 まとめ10選 (Vol. 3)

1. 砂場のピエロ
夏休みに入り、娘のミオは近所の公園の砂場がお気に入りだった。毎日、小さなスコップとバケツを手に「お砂場遊び行く!」とせがむので、私も日課のように付き合っていた。ある日、いつものようにミオが砂山を作っていると、公園の隅に移動販売の車が停まった。鮮やかな赤と白のストライプ。風船を持ったピエロが、車の窓から顔を覗かせている。「ハーイ!みんな、遊びに来てねー!」と、甲高い声が響く。ミオは「ピエロさんだ!」と目を輝かせ、たちまち夢中になった。
ピエロは毎日同じ時間に公園にやってきた。最初は遠巻きに見ていた子供たちも、親しげな態度と無料で配られる小さな風船に惹かれ、すぐにピエロの周りに集まるようになった。ミオも例外ではなかった。「パパ、今日のピエロさん、ねこのお顔だったんだよ!」と、毎日違う動物のメイクで現れるピエロの顔を、目を輝かせて報告してくれた。私も、子供たちを楽しませるピエロのプロ意識に感心していた。彼は子供たちの名前をすぐに覚え、特にミオには優しく声をかけてくれた。「ミオちゃん、今日も可愛いね!何を作ってるの?」
そんな日が数週間続いたある夕方、事件が起きた。ミオが砂場で遊んでいると、突然「キャアアアア!」という絶叫が公園に響き渡った。見ると、ブランコで遊んでいた男の子が、勢い余って地面に落ち、頭から血を流している。他の子供たちはパニックになり、泣き叫ぶ声が響く。私も急いで駆け寄ろうとしたその時、ピエロが男の子の元へ一番に駆け寄った。彼は素早くハンカチを取り出し、男の子の頭を押さえた。「大丈夫、大丈夫だよ。すぐ救急車を呼ぶからね」ピエロの落ち着いた声が、一瞬で場の混乱を鎮めた。
救急車が到着し、男の子が運ばれていくのを見届けた後、公園には重い静寂が訪れた。子供たちも帰り、残ったのは私とミオ、誠してピエロだけだった。「大丈夫でしたか…?」私が声をかけると、ピエロは俯いたまま、力なく首を振った。「子供の怪我は、見てるこっちも辛いね。特に顔に傷が残るようなことになったら…」彼の顔は、いつもの笑顔ではなく、深い悲しみに覆われていた。その日、ミオは珍しく口数が少なかった。
夜になり、ミオはベッドに入ってからも落ち着かない様子だった。「パパ、あのね…」と、小さな声で話し始めた。「今日、ピエロさん、お化粧してなかったんだよ」。私はその言葉に首を傾げた。(いつも凝ったメイクをしているのに、今日は違ったのか?)そんなことを考えていると、ミオはさらに続けた。「それでね、頭から血が出てる男の子の顔を見たとき…ピエロさん、笑ってたんだよ」。私はミオの言葉の意味が理解できず、ただ混乱したまま、隣で眠る娘の顔を見つめることしかできなかった。
なぜ怖いのか?
一見、子供好きなピエロが怪我をした子供を心配する話に見える。しかし、ミオの「ピエロさん、お化粧してなかった」という証言が、ピエロの真の目的を暗示している。 このピエロは、子供を楽しませるのが目的ではなく、子供の「顔」に異常な執着を持つ猟奇的な人物である。彼は、子供たちの「無垢な顔」を観察し、怪我や事故によってその顔が「歪む瞬間」や「傷つく姿」を見る機会を待っていた。普段のメイクは、子供たちを安心させ、自分を「無害な存在」として認識させるためのカモフラージュに過ぎない。絶叫が響き渡った際、彼が一番に駆け寄ったのは、助けるためではなく、男の子の「傷ついた顔」を間近で見るためだったのだ。メイクをしていなかったのは、素の感情が抑えきれず、衝動的に現場に駆けつけたためか、あるいはそれが彼の「素顔」であり、子供の不幸に直面した時にこそ現れる「真の顔」だったのかもしれない。主人公は、娘の無邪気な証言によって、日常に潜む純粋な悪意の片鱗を突きつけられたのだ。
2. 霧の中の供物
今日は祖母の一周忌だった。母と二人、少し早く実家を出て、裏山にある古びたお墓へ向かった。山道に入ると、朝だというのに妙に冷え込んでいた。この時季にしては珍しく、濃い霧が立ち込めていて、数メートル先も見通せない。母は「この霧も、おばあちゃんが呼んでいるみたいね」と笑ったが、その声はどこか強張っているように聞こえた。墓地に続く石段を登る。辺りは静寂に包まれ、墓石のシルエットがぼんやりと霧の中に浮かんでいる。
先週、二人で掃除に来たはずなのに、墓石はまた薄く埃をかぶっていた。母は慣れた手つきで水をかけ、ブラシで丁寧に磨き始めた。「お供え物、何にしたの?」と聞くと、母はリュックから白い紙に包まれた包みを取り出しながら答えた。「おばあちゃんが大好きで、亡くなる直前まで食べていた、あの『大きな赤い果物』よ。この季節だと手に入りにくいんだけど、いつもお世話になっている八百屋さんが特別に用意してくれたの。
墓石の前に清めた供物を並べ、線香をあげ、手を合わせた。濃い霧のせいで、周囲のお墓はほとんど見えず、自分たち以外誰もいないような錯覚に陥る。手を合わせ終わると、母は言った。「さあ、早く帰りましょう。こんなに霧が深いと、足元が危ないわ。それに、ご近所への挨拶回りもあるんだから」。急かされるように、私たちは墓地を後にした。山道を下り、霧が薄れていくのを感じながら、私はふと、母の言葉を思い出した。
あの『大きな赤い果物』。祖母は確かに大好きだった。しかし、ふと視界の端に映った、実家の玄関の隅に置いてあった日めくりカレンダーの日付を私は認識した。そういえば、亡くなる少し前の祖母は、体調を崩して寝たきりになって以来、固形物を一切口にできなくなっていたはずだ。あの時の献立は、いつも流動食ばかりだった。あの時、母は、なぜあんなに嬉そうに「おばあちゃんが好きだった」と、あの『大きな赤い果物』を包んでいたのだろうか。足元を覆う霧のように、その違和感が頭の中にじわりと広がり、全身の血の気が引くのを感じた。
なぜ怖いのか?
「固形物を口にできなかったはずの祖母」に対して、母が「亡くなる直前まで祖母が食べていた」と発言があります。それは、母による意図的な殺害の可能性を暗示しています。母は、祖母が固形物を摂取できないことを知りながら、あるいはそれが致命的になると知りながら、祖母が強く求めていたその果物を「最後の願い」として与えてしまった。母にとって、この果物は「殺意の証拠」であり、「とどめの一撃」を象徴しています。一周忌に供物を捧げた行為は、祖母への供養ではなく、罪の意識を封印するための儀式だったのです。主人公が気づいた矛盾は、母の行動が愛情ではなく、恐ろしい秘密に基づいていたことを示しています。
3. 押入れの奥の記録
私は極度の潔癖症で、私物はすべて、押入れの中に整頓して収納していました。最近、どうにも集中力が続かず、ストレスで幻覚を見ているのではないかと疑い始めていました。ある朝、押入れを開けると、私物を入れていた箱の隅に、血が滲んだ「爪」の破片が落ちているのを見つけました。潔癖な自分がこんなものを放置するはずがないのに。
「気のせいだ」と自分に言い聞かせ、破片を捨てました。しかし、その夜、押入れの奥から微かに「囁き」声が聞こえたんです。「全部、私のせいだ」。それは、過去に職場で犯した失敗を責める、自分の声に聞こえました。私は罪悪感からくる幻覚だと決めつけ、耳を塞ぎました。
翌朝、顔を洗おうと洗面台に向かうと、「ティッシュ」の箱の蓋に、細かく削られた「爪」の粉末が付着しているのを発見したんです。思わずゾッとしました。自分の爪は短い。一体、誰が、何のために?私はすぐに押入れに戻り、過去のスケジュールを記録していた手帳を引っ張り出しました。数週間前の日付の欄に、震える筆跡で、『今日は、〇〇を削いだ日』と書かれていました。
「〇〇」の部分は、カッターで強く削られて読み取れない。そのとき、私は自分の爪が異常に短いことに気づきます。私は「幻覚」を見ているのではなく、「幻覚」を装い、「無意識」のうちに自己加害を行っていたことを悟ったんです。押入れの扉を閉めようとした瞬間、鏡に映った自分の「顔」を見たんです。そこには、自分の爪で必死に「皮膚」を引っ掻いた、新しい「傷跡」が深く刻まれていました。
なぜ怖いのか?
一見、潔癖症の主人公がストレスから「幻覚」に悩まされる話に見えますが、核心的な違和感は「爪の破片が自分のものなのに、自分で捨てた記憶がない」ことと、「手帳に残された自罰的な記述」です。主人公は、過去の罪悪感から逃れるため、解離性健忘に近い状態に陥っており、無意識のうちに自己加害を行っていたのです。押入れは、彼女の「罪と罰を隠す場所」でした。手帳の記述は、その無意識の別人格が「記録を残そう」とした物理的な証拠。主人公が最後に見た「顔の傷跡」は、彼女の無意識の自罰行為が、もはや「幻覚」では隠し通せないレベルに達していたことを示しています。彼女は、自分自身から逃げられない恐怖に直面したのです。
4. ミラーに映る追跡者
タケシは深夜、郊外の山道を運転していました。周囲は街灯がなく、車のヘッドライト以外は真っ暗です。過去の事故のせいで、彼は運転中、常にサイドミラーで背後を確認する癖がついていました。
坂道を下っている最中、突然、車体の下から「ドン!」という鈍い音が発生しました。タケシは動物でも撥ねたのかと血の気が引きましたが、車体に異常はなく、「気のせいだ」と判断し走り続けます。その直後から、右腕に強い痛みを感じ始めました。事故のショックで肩を痛めたのだろうと考えました。
痛みをこらえ運転を続けますが、右腕の痛みが異常に増していきます。ふと、サイドミラーを見ると、背後が「真っ暗」なはずの車道に、微かに何か「白いもの」が這うように動いているのが見えました。驚いて車を停めると、右腕の袖口から小さな血が滲んでいます。鋭利な刃物で抉られたような傷が走っていました。
タケシは血と痛みで混乱しながらも、ふと、サイドミラーを見ました。ミラーの表面には、小さな「ヒビ」が入っています。そして、彼は決定的な矛盾を思い出したんです。「ドン!」という音がした瞬間、彼は反射的に右腕で顔を庇ったはずですが、その時、右腕には何の「痛み」も感じなかった。右腕の痛みが始まったのは、音が鳴ってから「数秒後」でした。
なぜ怖いのか?
一見、深夜の運転中に事故を起こした話に見えますが、決定的な違和感は「音と痛みの時間差」と「サイドミラーのヒビ」です。「ドン!」という音は、主人公を狙う追跡者が車体にぶつかった音です。主人公は過去のトラウマから、これを反射的に「事故」と記憶を上書きしました。右腕の傷は、追跡者が車を停めるため、窓の外から主人公の右腕を刃物で傷つけた警告の痕跡です。サイドミラーのヒビは、追跡者が車に張り付くためにミラーを掴もうとして割った物理的な証拠。主人公が最後に気づいたのは、自分が事故を起こしたのではなく、追跡者が今も車の「外側」に張り付いているという、逃げ場のない恐怖でした。
5. 真夜中の再会
午前2時過ぎ。深夜のコンビニでのバイトは、この時間が一番静かだ。自動ドアの開閉音だけが、BGMのJ-POPを時折遮って店内に響く。俺は欠伸を噛み殺しながら、雑誌コーナーの整理をしていた。客はもう30分近く来ていない。
「チリンチリン」 不意にドアが開き、入ってきた男を見て俺は少し驚いた。中学時代の同級生、サトウだった。 「あれ、タナカ? 久しぶり! こんなとこでバイトしてたんだ。いやあ、偶然だなあ」 サトウは人懐っこい笑顔で、大げさに驚きながら俺に話しかけてきた。正直、中学時代はクラスが一緒だっただけで、ほとんど話した記憶がない。卒業以来、一度も会っていなかったはずだ。それなのに、まるで親友に再会したかのようにやけにフレンドリーだった。 「ああ、うん。夜勤でさ」 「そっか、大変だな。夜道とか危なくない? 俺も今、仕事の帰りなんだ。ちょうどこっち方面だからさ。じゃ、これお願い」 サトウは缶コーヒーを一本だけレジに置いた。 「頑張ってな!」 会計を済ませると、サトウは笑顔で手を振り、夜の闇に消えていった。
午前3時。きっかりにバイトが終わり、俺は裏口から出た。防犯マニュアル通り、人目につかないように裏道を通って帰る。冷たい夜気が肌を刺す。 家までの帰り道は、街灯もまばらな住宅街だ。歩き始めて5分ほど経っただろうか。ふと、背後に足音を感じた。 (……気のせいか?) だが、足音は消えない。アスファルトを擦るような、妙に粘ついた音だ。振り返る勇気はなく、ただ歩調を速める。しかし、その足音も同じように速くなり、一定の距離を保ったまま確実についてくる。 (まさか…) さっきのサトウの顔が浮かぶ。いや、彼はとっくに帰ったはずだ。 恐怖に駆られ、俺は走り出した。後ろの足音も、間髪入れずに走り出す。
息を切らして自宅マンションのエントランスに滑り込む。オートロックの重いドアが閉まる音に心底安堵し、荒い息を整えながら外の暗闇を睨んだ。もう誰もいない。 (ただの通り魔か…? いや、でも…) そう思いかけた瞬間、俺は凍りついた。 さっきのコンビニでの会話が、鮮明に蘇る。
『俺も今、仕事の帰りなんだ。ちょうどこっち方面だからさ』
サトウが店に来たのは、午前2時15分。 俺のバイトが終わったのは、午前3時。 「帰り」のはずのサトウは、あの後45分間、一体どこにいたんだ…?
なぜ怖いのか?
サトウは「偶然」を装い、「仕事の帰り」だと主人公に告げた。もし本当に仕事帰りで、主人公と「こっち方面」に帰るだけなら、午前2時15分に缶コーヒーを買った後、そのまま帰宅するはずである。 しかし、主人公がバイトを終えて裏口から出た午前3時、何者かが主人公を「ついてきた」。 つまり、サトウは「仕事の帰り」というのは嘘であり、主人公のバイトが終わるのを意図的に待っていたことになる。彼は午前2時15分から午前3時までの45分間、コンビニの近くの暗闇で、主人公が出てくるのをずっと待ち伏せしていたのだ。 「夜道とか危なくない?」という言葉は、一見すると親切な心配のようだが、今思えば「これから自分が実行すること」を仄めかす不気味な問いかけだった。 特に親しくもなかった同級生が、なぜ自分のバイト先と勤務時間を正確に把握し、45分も真夜中に待ち伏せしてまで後をつけてきたのか。その目的は、主人公にはまだ分からない。
6. 穴の向こう
俺が住むアパートの隣室に、若い母親と5歳くらいの男の子が引っ越してきた。「こどもがまだ小さくて。もしかしたら、真夜中に騒いだりしてご迷惑をおかけするかもしれません」と、母親は深々と頭を下げた。俺は「お互い様ですよ」と当たり障りのない挨拶を返した。
だが、引っ越してきてから一週間、隣からは物音一つしない。子供がいるとは思えないほど静かで、かえって不気味なくらいだった。 ある夜、残業で終電近くに帰宅すると、自室のドアの前にその男の子が一人でちょこんと座り込んでいた。 「どうしたの? こんな時間に。ママは?」 「ママ、お買い物。これ、おにいちゃんにって」 男の子は眠そうな目をこすりながら、小さな手でお菓子の袋を差し出した。お裾分けらしい。 「ありがとう。でも、ママが帰ってくるまで、お部屋で待ってなきゃ危ないよ」 「ううん。ママがね、おにいちゃんのお部屋の『のぞきあな』を見てなさいって」
俺は一瞬、男の子が何を言っているのか理解できなかった。 「…覗き穴を?」 「うん!」男の子は無邪気に頷いた。「ママがね、『あそこが暗くなったら、おにいちゃんが帰ってきた合図だから。そしたら、これ渡してね』って」 よく分からない理屈だったが、小さな子供の言うことだ。俺は「そか。教えてくれてありがとう」とだけ言い、お菓子を受け取って部屋に入った。
その日の真夜中。俺はふと喉の渇きを覚えて目を覚ました。水を飲もうとリビングから廊下に出た、その瞬間。 玄関のドアが視界に入った。 ドアの覗き穴が、外側から「何か」で塞がれるように、ほんの一瞬、カゲった気がした。 (まさか…) 俺は息を殺してドアに近づき、恐る恐る覗き返した。そこには、非常灯に照らされた、誰もいない静かな廊下が広がっているだけだ。 (気のせいか…疲れてるんだな) 安堵した俺は、リビングに戻ろうとした。その時、昼間の男の子の言葉が、不意に脳裏に蘇った。
『あそこが暗くなったら、おにいちゃんが帰ってきた合図だから』
(…なんで?) (外から覗き穴を見ても、俺が帰ってきたかなんて分からないはずだ。普通、合図にするなら、「部屋の電気がついたら」とかじゃないのか…?) (「暗くなったら、帰ってきた合図」…?)
(…「あそこ」って、いったいどこから見てるんだ…?)
なぜ怖いのか?
男の子の『あそこが暗くなったら、おにいちゃんが帰ってきた合図だから』という言葉が、この話の恐怖の核心である。 母親は男の子に、「隣の部屋(主人公の部屋)の覗き穴を、外からずっと覗き続ける」ように指示していたのだ。 そして、主人公が帰宅した際、外の気配(子供の姿)に気づき、不審に思って「内側から覗き穴を覗き返す」だろうと予測していた。 主人公が内側から覗き穴を覗いた瞬間、外から見ている男の子にとっては「穴が(主人公の目で塞がれて)暗くなる」。 母親はそれを「帰宅の合図」だと、男の子に教えていたのである。
7. 染みついた香り
同棲を始めた彼氏のケントは、少し潔癖症だ。几帳面で、特に水回りの清潔さには強いこだわりがある。でも、そのぶん家事も完璧にこなしてくれるし、私にはとても優しい。 「ユミは髪が長いから、排水溝の掃除だけはちゃんとしてね」 それが彼の唯一の口癖だった。
ある夜、私が風呂から上がると、ケントが脱衣所で待っていた。 「あ、ごめん。風呂のふた、半分開けっ放しにしちゃった」 「ううん、大丈夫。でも、湿気がこもるとカビの原因になるから、次から気をつけて」 ケントは優しく笑いながら、きっちりとフタを閉めた。 最近、ケントは新しい入浴剤を大量に買ってきた。ラベンダーの、かなり香りが強いタイプだ。 「これ、すごくいい匂いだから。ユミ、仕事で疲れてるだろ? リラックスできるよ」 その日から、浴室は常にラベンダーの強い香りで満たされるようになった。
数日後の夜。入浴剤を使った私が風呂から上がると、ケントがいつもより真剣な顔で浴室を覗き込んでいた。 「どうしたの?」 「いや…なんというか、匂いが…」 「え? ラベンダーのいい匂いしかしないけど…」 「ううん、違うんだ。その奥の…排水溝からかな。なんか、独特の…鉄っぽいような…」 ケントは神経質そうに鼻をひくつかせ、排水溝のフタを開けて何かを確認している。 「ごめん、何でもない。気のせいだ」 彼はそう言って、浴室のドアをピシャリと閉めた。その日から、彼は私が風呂に入るたび、「今日はあの入浴剤、ちゃんと使ってね」と念を押すようになった。
週末、ケントが先に風呂に入った。私はリビングでテレビを見ていたが、ふと、浴室の方から「ゴシ、ゴシ」と何かを擦る音が微かに聞こえるのに気づいた。 (もう上がったのかな? 掃除してる?) 様子を見に行くと、浴室のドアが少しだけ開いていた。 「ケントー? お湯加減どう…」 言いかけて、私は固まった。 ケントは浴槽に浸かっていなかった。彼はTシャツ姿のまま、風呂のふたを一枚だけ外し、その隙間から何か細長いブラシのようなもので、浴槽の底の排水溝(栓)のあたりを必死に擦っていた。 そして、彼は独り言を呟いていた。
「ダメだ…この匂い…どうしても取れない…なんで…あいつと同じ匂いがするんだ…」
(…あいつ?) (同じ…って、何が?)
その時、ケントが買ってきたあのラベンダーの入浴剤の強烈な香りが、浴室の湿気と共に私の鼻を突いた。
(…まさか) (あの入浴剤って、私がリラックスするためじゃなくて…) (この「匂い」を消すために…?)
なぜ怖いのか?
ケントの行動は「潔癖症」ではなく、「証拠隠滅」の強迫観念からくるものだった。 彼は過去に「あいつ(=元カノなど)」をこの浴室で殺害し、遺体を処理した。その際、血や体臭が排水溝に染みついた(と彼は思い込んでいる)。 彼が「潔癖症」のように振る舞い、排水溝の掃除に執着していたのは、汚れを落とすためではなく、トラウマとなった「匂い」を消すためである。 主人公が同棲を始め、風呂を使い始めたことで、湿気や体温によって(彼の幻想の中の)「匂い」が蘇ってきたと感じ始めた。 「あいつと同じ匂いがする」というのは、主人公からも「あの時と同じ匂い」がするという、彼の妄想である。 ラベンダーの入浴剤は、リラックス効果のためではなく、その強烈な香りで「匂い」をマスキングするために買ってきたものだった。 「風呂のふた」を閉めることにこだわったのも、カビ対策ではなく、匂いを浴室に閉じ込めるためだ。 結びの場面、ケントはTシャツ姿だった。つまり彼は入浴していたのではなく、主人公が入る前に「匂い」を消そうと必死に掃除していたのである。
8. 深夜の親切
会社の飲み会が長引き、深夜になってしまった。終電はもうない。私は結構な量のお酒を飲んでしまい、少しクラクラする頭でタクシーを拾おうと大通りに向かって歩いていた。
人気のない道端の電柱に、一人の酔っ払いが寄りかかっていた。スーツ姿の、人の良さそうなサラリーマン風の男性だ。 彼が私に気づき、申し訳なさそうに話しかけてきた。 「あー、お姉さん。ごめん、ちょっといいかな?」 「はい?」 「悪いんだけど、スマホ貸してくれない? さっきからカミさんに電話してるんだけど、俺の、電池切れちゃって。これ以上遅くなると本気で怒られるんだ」 彼はそう言って、画面の暗いスマホを私に見せた。かなりお酒臭いが、口調は丁寧だ。
深夜にスマホを貸すのは少し怖かったが、奥さんへの連絡なら仕方ない。私は少し距離を取り、カバンから自分のスマホを取り出した。 「ありがとうございます、助かります。えーっと…」 彼は私のスマホを受け取ると、電話番号を打ち込もうとする。だが、ひどく手が震えており、うまく画面をタッチできないようだ。 「…ダメだ、手が震えて番号が押せない。本当に本当に申し訳ないんだけど、代わりに押してもらえないかな? 090-XXXX-XXXX(11桁)です」 「あ、はい。いいですよ」
私は彼からスマホを受け取り直し、言われた番号を打ち込んで発信ボタンを押した。 コール音が数回鳴ったが、相手は電話に出なかった。 「…出ないみたいですね」 「ああ、そうか…。もう寝ちまったかな。すまないね、親切にしてもらったのに。本当にありがとう」 彼は何度も頭を下げ、私のスマホを受け取ると、おぼつかない足取りで夜道に消えていった。
私はホッとして、再び大通りに向かって歩き出した。 その時、ふと強烈な違和感が背筋を走った。
(あれ…?) さっきの男性の言葉が、妙にハッキリと耳に残っていた。
『手が震えて番号が押せない』
(…手が震えるほど泥酔してるのに) (なんで、あんなにハッキリとした口調で、奥さんの11桁の電話番号を、一言も間違えずにスラスラと暗唱できたんだろう…?)
なぜ怖いのか?
男は酔っ払いのフリをしていただけである。 彼の目的は、深夜に一人で歩いている女性(主人公)の電話番号を手に入れることだった。 「手が震えて番号が押せない」というのは、主人公に電話番号を打ち込ませ、発信させるための巧妙な演技である。 もし主人公が「番号を教えてくれれば、私の方でかけますよ」と申し出ても、男の目的は達成される。 男が告げた番号は「奥さんの番号」などではない。それは、男がポケットに隠し持っている「もう一台のスマホ」の番号だ。 主人公がその番号に発信した瞬間、男のもう一台のスマホには、主人公の電話番号が「着信履歴」として完璧に記録された。 「誰も出ない」のは当たり前である。男は、自分のポケットの中で鳴っているスマホを無視していただけなのだから。 これで男は、「深夜に一人で歩いており、かつ警戒心が薄く親切な女性」の電話番号を、安全かつ確実に入手したことになる。
9. 見守る人
私の所属する部署は、いつもピリピリしている。そんな中で、唯一の癒しが、別の部署の佐藤上司だ。彼は定年間近の年配の男性で、いつもニコニコと穏やかだ。私が給湯室でため息をついていると、よく「まぁ、頑張りすぎなさんな」と缶コーヒーを差し入れてくれる、優しい人だ。
佐藤上司は少し変わっていて、PCが苦手だと公言している。連絡事項はいつも、小さな付箋メモに手書きだ。私の机にも、よく「お疲れ様」「無理するなよ」といった励ましのメモが貼られていることがあった。誰が貼っているのかは謎だったが、筆跡で佐藤上司だと分かった。離れた部署からわざわざ歩いてきて、こっそり置いていってくれる。その親切が嬉しかった。
その日、私は大きなミスをした。重要なプレゼン資料の最終版で、クライアントの名前を間違えるという、取り返しのつかないミスだ。幸い、社内レビューの段階で気づいたが、私は自分の机で頭を抱えていた。 (どうしよう、また信用をなくしちゃった…) 血の気が引いていくのが分かった。その時、肩をポンと叩かれた。 佐藤上司だった。 「どうした、顔が真っ青だぞ」 「あ、部長…いえ、なんでもないです」 「なんでもない顔じゃない。ほら、これでも飲んで落ち着け」 彼はいつもの缶コーヒーを私に手渡した。私は席に座ったまま、それを受け取った。 「ありがとうございます…」 「焦ってもいいことはない。大丈夫、お前さんならできる」 彼はそう言って、穏やかに笑い、自分の部署の方へ戻っていった。
私は少しだけ落ち着きを取り戻し、コーヒーのプルタブに指をかけた。 その時、視界の端、PCモニターのフレームに貼られた真新しい付箋メモに気づいた。 さっきまで、そこには絶対に何も貼られていなかったはずだ。
見慣れた、佐藤上司の丸い筆跡だった。
『2ページ目の社名が違うぞ』
(…え?)
私は凍りついた。 (なんで、それを知ってるの…?)
なぜ怖いのか?
佐藤上司の「親切な年配の善人」「PCが苦手」という人物像は、すべて偽りである。 彼は(おそらく社内システムへの不正アクセスやスパイウェアによって)主人公のPCをリアルタイムで監視しており、主人公の行動、ミス、そして心理状態をすべて把握している。 彼がいつも「完璧なタイミング」で現れ、励ましの言葉をかけられたのは、偶然や「顔色」で判断していたからではなく、監視しているPC画面で「ミスを発見した」からである。 今回の恐怖の核心は、「メモが貼られたタイミング」にある。 佐藤上司は、主人公がミスに気づき動揺しているのを確認した後、コーヒーを持って現れた。しかし、彼は主人公と会話するだけで、メモを貼る物理的な動作は一切行っていない。 主人公が「癒し」だと思っていた励ましのメモも、すべて監視下で行われた「飼育」のようなものだった。
10. 親切なタイマー
一人暮らしを始めてから、この古い中古のテレビには少し困っていた。毎日、決まって夜11時になると、勝手につくのだ。 チャンネルはいつも同じ。地元のローカル局がやっている「おやすみ前の天気予報」。
最初は少し気味が悪かったが、慣れてくると便利に思えてきた。「あ、もうこんな時間か」と寝る準備の目安になるし、天気予報を確認してから眠れるのは「親切」な機能だとさえ思っていた。 (前の持ち主がオンタイマーを設定したままなんだろうな。まあ、いっか) 私はそう結論づけて、特に設定をいじることもしなかった。
ある週末、彼氏が泊まりに来た。夜11時。私が「あ、そろそろつくよ」と言った瞬間、パッとテレビがついた。いつもの天気予報だ。 「へえ、すごい。オンタイマーだけじゃなくて、チャンネルまで固定なんだ。古いのに高機能だね」 彼氏は感心しながらリモコンを手に取った。 「ちょっと設定見てみるよ。…あれ?」 彼氏がリモコンを操作しながら、怪訝な顔をする。 「どうしたの?」 「いや…このテレビ、タイマー設定の項目自体が『オフ』になってる」 「え? じゃあなんでつくの? 接触不良?」 「かもな。あ、天気予報終わった」 彼氏はそう言うと、リモコンで別のチャンネル(深夜のバラエティ番組)に変えた。私たちはそのままダラダラとそれを見て、夜中の1時頃、彼氏がリモコンで電源を切って寝た。
翌朝、彼氏は帰っていった。 その夜。私は風呂から上がり、髪を乾かしていた。時計は10時59分。 (そういえば、昨夜は彼氏がチャンネル変えたままだったな) (11時になったら、昨日のバラエティ番組がつくのかな? それとも、さすがにつかないか) ボン、と壁の時計が11時を指した。
「こんばんは。おやすみ前の天気予報です」
(……え?)
私は、ドライヤーを持ったまま凍りついた。 テレビは、いつものローカル局の天気予報を映し出していた。
(なんで…?) (タイマーは「オフ」だったはずじゃ…)
(それに…) (昨夜、彼氏が確かにチャンネルを変えて、リモコンで電源を切ったのに) (どうやって「時間通り」について、どうやって「チャンネル」を天気予報に“戻した”の…?)
なぜ怖いのか?
このテレビは、故障やタイマーの誤作動でついていたのではない。 主人公の家の外(隣室、あるいはアパートの廊下や向かいの建物など、赤外線が届く範囲)から、第三者が「学習リモコン」や「スマートリモコン」を使って、意図的に操作していたのだ。 犯人(ストーカー)は、主人公が毎日その時間に在宅しているかを確認するために、テレビをつけていた。 「天気予報」という無害な番組を選ぶことで、主人公に「便利なタイマー機能(親切)」だと思い込ませ、警戒心を解いていた。
最後に

いかがでしたか?
笑顔のピエロ、お墓参りの供物、そして親切な上司。それら日常に溢れる「善意」や「優しさ」の裏側が、実は綿密に計画された「誰かの狂気」に基づいていることが、何よりも恐ろしいのかもしれません。
「狂気の館」では、あなたの日常を破壊するようなショートホラーを、今後も量産していきます。





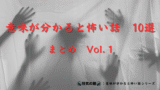



コメント