お話
見知らぬ土地での一人旅は、私の悪い癖だった。案の定、ガイドブックにも載っていない山道を散策しているうちに、完全に道に迷ってしまった。時刻はもう夕方。オレンジ色の光が木々の隙間から差し込み、急速に気温が下がっていくのが分かる。スマホはとっくに圏外だ。
途方に暮れて泣きそうになった時、畑仕事帰りらしい、人の良さそうなおばあさんに出会った。 「あらあら、お嬢さんどうしたの? 道に迷った? まあ、この時間からじゃバスもないし、麓まで歩くのは無理だよ」
「今夜はうちに泊まっていきなさい。何もないところだけどね」 おばあさんの善意に、私は心から感謝した。おばあさんの家に向かう細いあぜ道に、苔むした古い井戸があった。 「昔はね、この井戸がここの神様だったんだよ。今はもう誰も拝まないけどね」 おばあさんはそう言って、一瞬だけ井戸に向かって静かに手を合わせた。
家に着くと、おばあさんは温かいお風呂と、山菜の煮物や手作りの漬物といった素朴だが美味しい夕食を出してくれた。 「本当にありがとうございます。助かりました」 「いいのよ。困った時はお互い様だからね」 私はすっかり安心して、疲れもあってすぐに眠気が襲ってきた。
「明日の朝、一番のバスが出る時間に合わせて、車でバス停まで送ってあげるから。ゆっくりおやすみ」 おばあさんの優しい声に送られ、私は客間のふかふかの布団にもぐりこんだ。
しかし、夜中。 ふと、突き刺すような悪寒で目が覚めた。おかしい。部屋はストーブが焚かれていて暖かいはずなのに、体の芯が凍えるように寒い。 喉が渇いたので水を飲もうと起き上がると、廊下を隔てたおばあさんの部屋から、話し声が聞こえてきた。
こんな深夜に、誰かと電話だろうか。 「ええ、ええ…本当に助かりました。今度の子はとても素直で、手がかからなくて…」 楽しそうな、弾んだ声。 「はい、もちろん。明日も、ちゃんとご挨拶させますから」
私は違和感を覚えた。おばあさんの家は、電話回線を引いているようには見えなかった。 そっと襖を数センチだけ開け、廊下の先を覗き見る。 おばあさんは、電話など持っていなかった。 彼女は玄関の土間に立ち、外に向かって――そう、あの古い井戸の方向に向かって、嬉しそうに一人で話し続けていた。
そして、私は見てしまった。 おばあさんの背後、居間の壁に並んでかけられた、いくつものカレンダーを。 それはすべて、去年の日付――2024年のまま、一枚も破られていなかった。
解説
一見、道に迷った主人公が親切なおばあさんに助けられる話に見える。 しかし、違和感は「去年の日付のままのカレンダー」が「何枚も」かかっていること。 これは、主人公が「今日」道に迷ったのではなく、この家に来てから、あるいはこの村に迷い込んでから、少なくとも「一年以上」が経過していることを示唆している。 おばあさんは「親切」を装い、道に迷った旅行者(主人公)を家に招き入れ、井戸の神様(あるいは何か別の存在)への「生贄」として監禁していた。 主人公は、食事に混ぜられた薬か何かで記憶を混濁させられ、「道に迷った最初の日」を毎日繰り返させられている。 おばあさんの電話の相手は井戸の神様で、「今度の子(主人公)は素直で(逃げ出そうともせず)助かる」と報告していたのだ。「明日バス停に送る」という言葉は、一年以上毎日繰り返されてきた、果たされることのない嘘。主人公は明日も明後日も、ここから「帰れない」。
この記事は、「【解説付き】意味が分かると怖い話 まとめ 10選:日常の監視者の狂気」にも収録されています。 他の「意味が分かる怖い話」の物語も、ぜひご堪能ください。




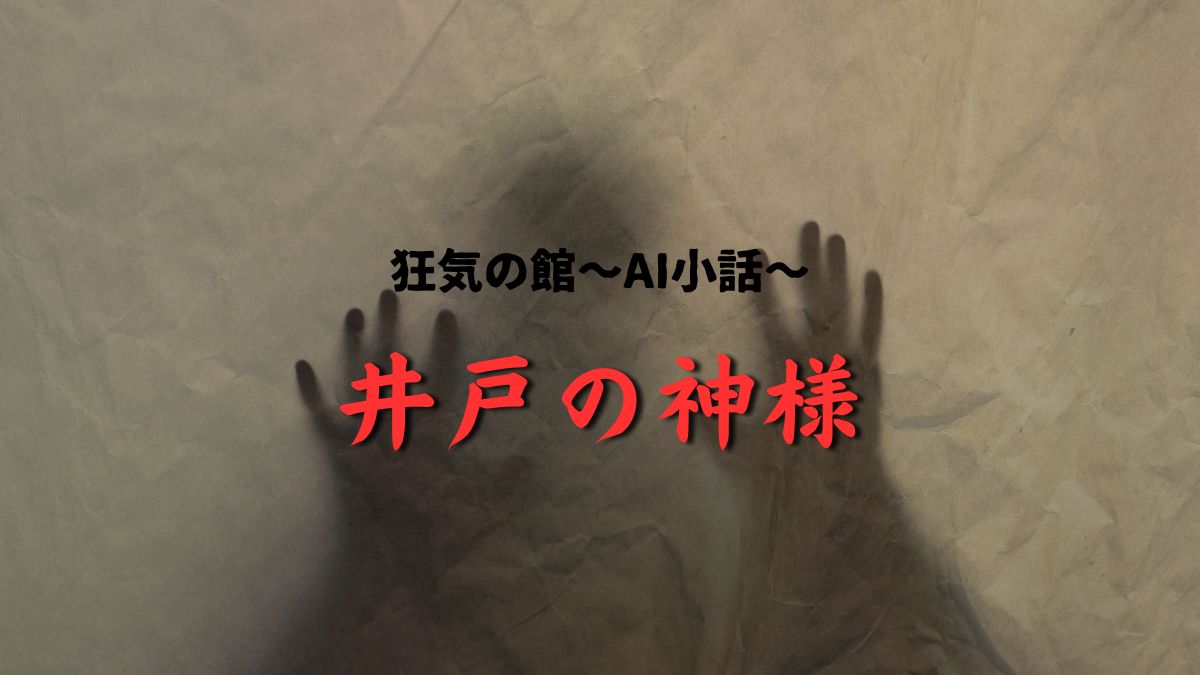


コメント