お話
俺は一週間前、アパートの階段で足を滑らせ、左の足首をひどく捻挫した。医者には「全治一ヶ月。絶対安静」と言われ、松葉杖生活を余儀なくされている。
そんな俺を、隣人の田中さんが毎日かいがいしく世話してくれていた。彼は俺より少し年上の、人の良さそうな男だ。「お互い様ですよ」と言って、毎日食事を運び、ゴミ出しまでしてくれる。本当にありがたい存在だった。
だが、怪我から一週間が経っても、足首の痛みが一向に引かない。それどころか、ズキズキとした鈍痛が、日に日に強まっている気がするのだ。医者にもらった痛み止めも、ほとんど効かない。
そのことを田中さんに相談すると、彼は「そうですか…それは心配だ」と眉をひそめた。 「あ、そうだ。僕、マッサージが得意なんですよ。血行を良くすれば、治りも早まるかもしれません。よければ今夜にでも」 俺は彼の親切に甘えることにした。
その夜、田中さんが部屋にやってきた。 「じゃあ、失礼しますね」 彼は俺の左足首を掴むと、ゆっくりと揉み始めた。しかし、その手つきは素人のマッサージとは程遠かった。指が的確に腱と骨の隙間に入り込み、痛みの芯を直接えぐってくる。 「いっ…! 田中さん、痛い、痛いです!」 俺は悲鳴を上げた。だが、田中さんは笑顔のまま、力を緩めない。
「あ、すみません。でも、ここが凝ってるんですよ」 彼は笑顔でそう言うと、さらに指に力を込めた。ゴリッ、と骨がきしむような嫌な音が響く。俺は激痛で身をよじった。 「やめ…やめてくれ!」 「ダメですよ、安静にしてないと」 田中さんは困ったように笑いながら、俺の足首を掴む手を離さない。 その時、俺はふと思い出した。彼が俺の部屋に入ってくるとき、いつも薄い壁一枚を隔てた彼の部屋から、微かに酸っぱいような異臭が漏れていたことを。 そして、一週間前に俺が階段から落ちたあの日。彼が真っ先に駆けつけ、俺の足首を「応急処置」してくれた時の、あの異常に手際の良い手つきを。 痛みと混乱の中、俺は親切な隣人の笑顔を、ただ見つめることしかできなかった。
解説
一見、親切な隣人がマッサージを失敗する(あるいは善意だが下手な)話に見える。 しかし、違和感は「一週間経っても悪化し続ける鈍痛」と、素人離れした「手際の良すぎる応急処置」。 主人公が階段から落ちたのは事故ではなく、隣人によって仕組まれたものだった。隣人は最初から主人公を「監禁」し「飼育」する目的で、まず足首を負傷させた。 そして、治癒を妨げる(あるいは悪化させる)薬物を食事に混ぜ、毎晩のマッサージと称して足首の腱や骨を意図的に破壊し、主人公が物理的に「逃げられない」状態を作り続けていた。壁の向こうの異臭は、以前の「獲物」が腐敗した臭いか、あるいは主人公のために用意された「何か」の臭いである。
この記事は、「【解説付き】意味が分かると怖い話 まとめ 10選:日常の監視者の狂気」にも収録されています。 他の「意味が分かる怖い話」の物語も、ぜひご堪能ください。




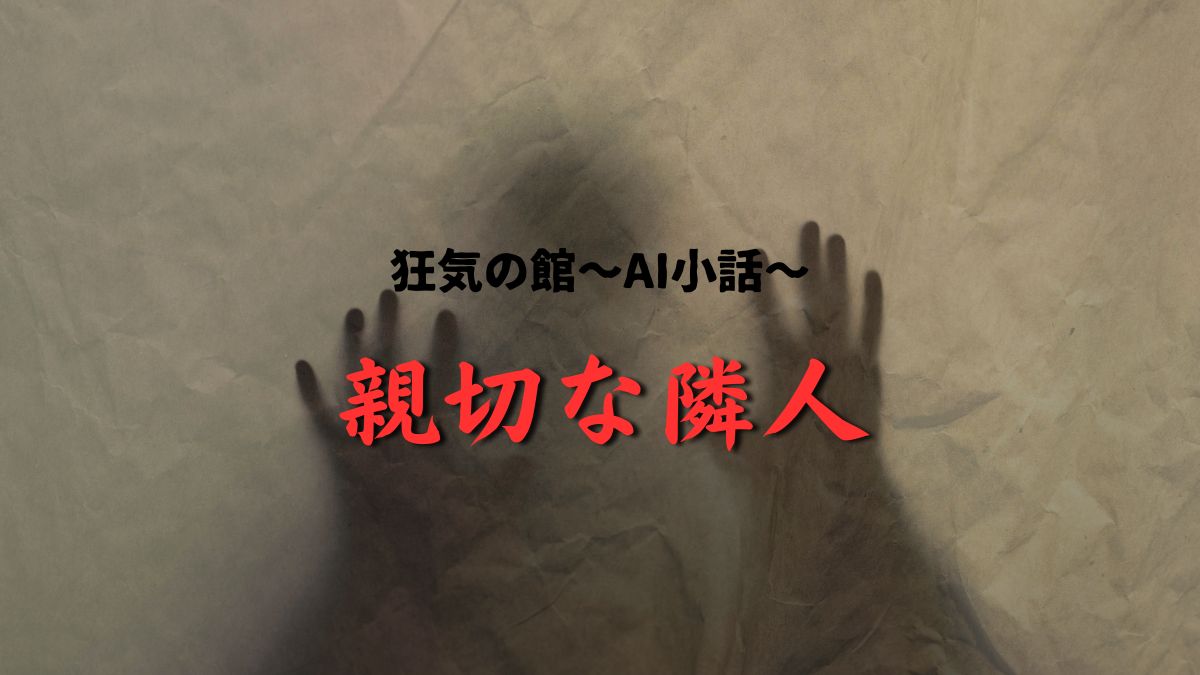


コメント