お話
最悪だった。飲み会が盛り上がりすぎ、気づけば「終電」はとっくに出ていた。おまけに、頼みの綱の「スマホ」は、カバンの中で冷たくなっており、充電が切れていた。家族や友人に連絡する手段もない。財布には数千円。明日は朝一番で大事な会議があるというのに。 「どうしよう……」 冷たい11月の雨が、アスファルトを叩き始めた。駅のロータリーには、あれほどいた「タクシー」が一台もいない。
絶望してうずくまりそうになった、その時だった。一台のタクシーが、路地の向こうからスーッと音もなく近づいてきて、私の目の前で停まった。 「どうぞ、乗ってください」 窓が開くと、人の良さそうな中年の運転手が、穏やかな声で言った。神様に見えた。 「ありがとうございます!」 慌てて乗り込むと、車内は暖房が効いていて、ほっと息が漏れた。
「どちらまで?」 私がアパートの住所を告げると、運転手は一瞬バックミラーで私を見て、「ああ、〇〇町の、あの角のパン屋さんの裏のアパートですね。承知しました」と、やけに具体的に返事をした。 (プロはすごいな、住所だけで分かるんだ) 深く考えず、私はシートに身を沈めた。 「大変でしたね、こんな時間まで。雨も強くなってきましたし」 「いえ、もう本当に助かりました…」 「疲れが出たんでしょう。よかったら、これどうぞ。サービスです」 そう言って、彼は車載の小さな保温庫から、温かい缶コーヒーを差し出してくれた。私は恐縮しながらも、その善意を受け取り、一口飲んだ。疲れた体に、甘いコーヒーが染み渡っていく。 そこからの記憶は、少し曖昧だ。よほど疲れていたのだろう。
気づくと、自宅のアパートの前に着いていた。「お客さん、着きましたよ」という声でハッと目を覚ました。 「すみません、寝てしまって…! おいくらですか?」 慌てて財布を出そうとすると、運転手はバックミラー越しにニッコリと笑った。 「いえいえ、こんな雨の日に頑張っているお嬢さんからは、とても貰えませんよ。今日はサービスです」 「そんな、悪いですよ!」 「いいんです。それじゃ、お気をつけて」 そう言うと、彼は私が降りるのを見届けて、雨の闇に静かに走り去っていった。 (世の中、まだ捨てたもんじゃないな…) 私は温かい気持ちで鍵を開け、部屋に入り、そのままベッドに倒れ込んだ。
翌朝。ひどい倦怠感で目が覚めた。まるで鉛を飲んだかのように体が重い。 そして、私は気づいてしまった。 玄関のタタキから、リビング、そして私が今寝ているベッドのすぐ脇まで、点々と、濡れた泥の「足跡」が続いているのを。昨夜は雨だった。私は確かに玄関で靴を脱いだはずだ。 ——その時、私は昨夜の「違和感」をぼんやりと思い出した。 「そういえば、あのタクシー……私が乗り込む前から、なんで『迎車』じゃなくて『賃走(※乗客が乗っているサイン)』の赤いランプが点いてたんだろう?」
解説
なぜ「賃走」だったのか? 運転手は、主人公のストーカーだったから。
彼は主人公の生活パターン(飲み会があること、終電の時間、スマホの充電が切らしやすい癖)を把握しており、駅前で「獲物」が助けを求めるのを待ち伏せていた。
彼が「賃走」ランプをつけていたのは、彼にとって「主人公を乗せること」自体が正規の営業ではなく、「主人公を(自分の支配下に置いて)家まで送り届ける」という個人的な「仕事(=賃走)」の最中だったから。
彼が住所の詳細を知っていたのも、コーヒー(睡眠薬入り)をサービスしたのも、すべて計画通り。料金を受け取らなかったのは、金銭が目的ではなく、眠っている主人公をベッドまで「運び」、無防備な姿を眺め、部屋に自分の「足跡」を残すことこそが真の「報酬」だったから。 彼は主人公の家の鍵を、すでに(以前侵入した際に)入手、あるいは複製している可能性が極めて高い。




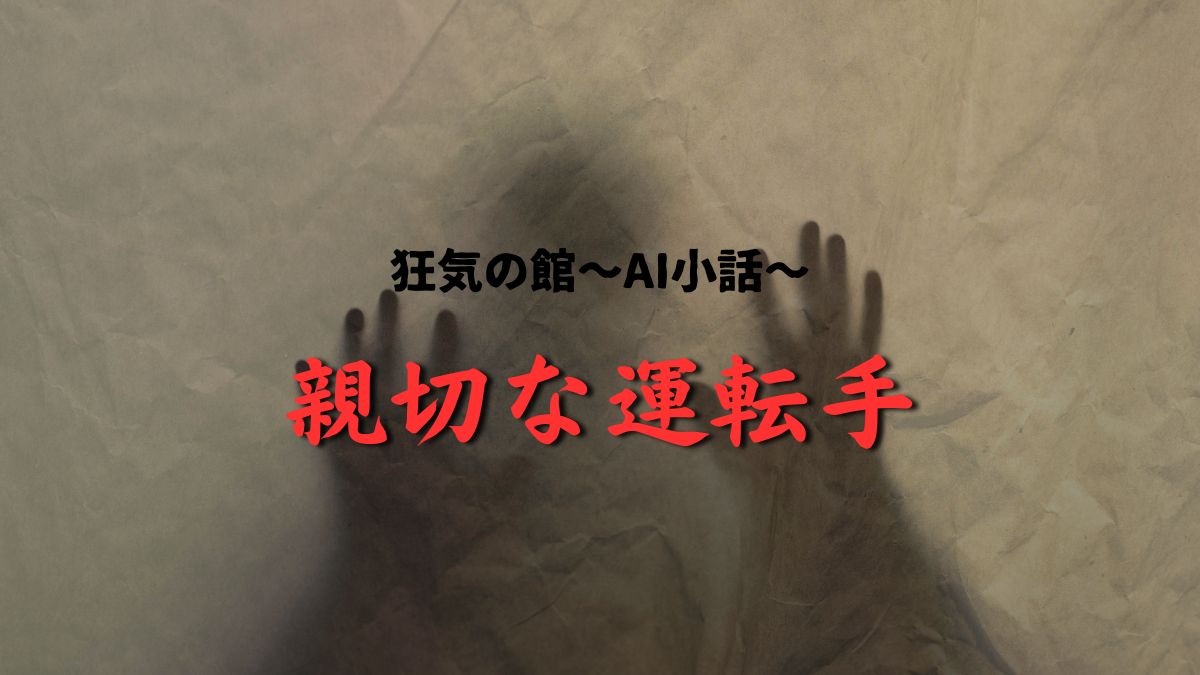


コメント