お話
休日の午後、私は近所の市立図書館を訪れていた。 そこは古いレンガ造りの建物で、奥まった場所にある学習コーナーは、人目も少なく集中するには最高の場所だった。
私は一番奥の席に座り、資格試験の勉強を始めた。しばらくすると、向かいの席に誰かが座る気配がした。顔を上げると、一人の男の子が大きな絵本を広げている。私は軽く会釈をし、再びノートに視線を落とした。
ふと、消しゴムを落としてしまった。 私は机の下を覗き込んだ。薄暗い床に転がった消しゴムを拾おうとしたとき、向かいに座る子の足が目に入った。 その足は、素足に古ぼけた「下駄」を履き、泥をつけたまま行儀よく揃えられていた。 (今どき、下駄を履いている子なんて珍しいな……) そう思いながら消しゴムを拾い、私は体を起こした。
「あ、ごめんね。驚かせちゃったかな」 声をかけると、男の子は絵本から顔を出し「ううん」と無邪気に笑った。 「お姉さん、さっきからずっと何か探してるでしょ。ボク、隠すの得意なんだ」 彼はそう言って、カバンを持って立ち上がった。
「もう帰らなきゃ。バイバイ!」 彼は元気に手を振ると、トコトコと軽快に走っていった。 廊下に響くのは、キュッキュッという「スニーカー」特有のゴムの音だ。
気になって振り返ると、開いたドアの向こう側、廊下を走っていく彼の足元には、どこにでもある「青いスニーカー」を履いていた。
私は、息が止まった。 ゆっくりと、自分の目の前にある「机の下」へ視線を落とす。 そこには、まだ誰も座っていないはずなのに…
解説
机の上で会話していた男の子は、青いスニーカーを履いた、どこにでもいる「普通の」元気な子どもだった。しかし、主人公が机の下を覗いたとき、確かにそこには「下駄を履いた足」が存在していた。つまり、机の上と下で全く別の存在が重なっていたか、あるいは男の子が座っている「すぐ真下」に、下駄を履いた何かが潜んでいたことになる。男の子が去った後に響くスニーカーの音が「普通」であればあるほど、机の下にいたはずの「下駄の主」だけが、まだその場所に残っている。




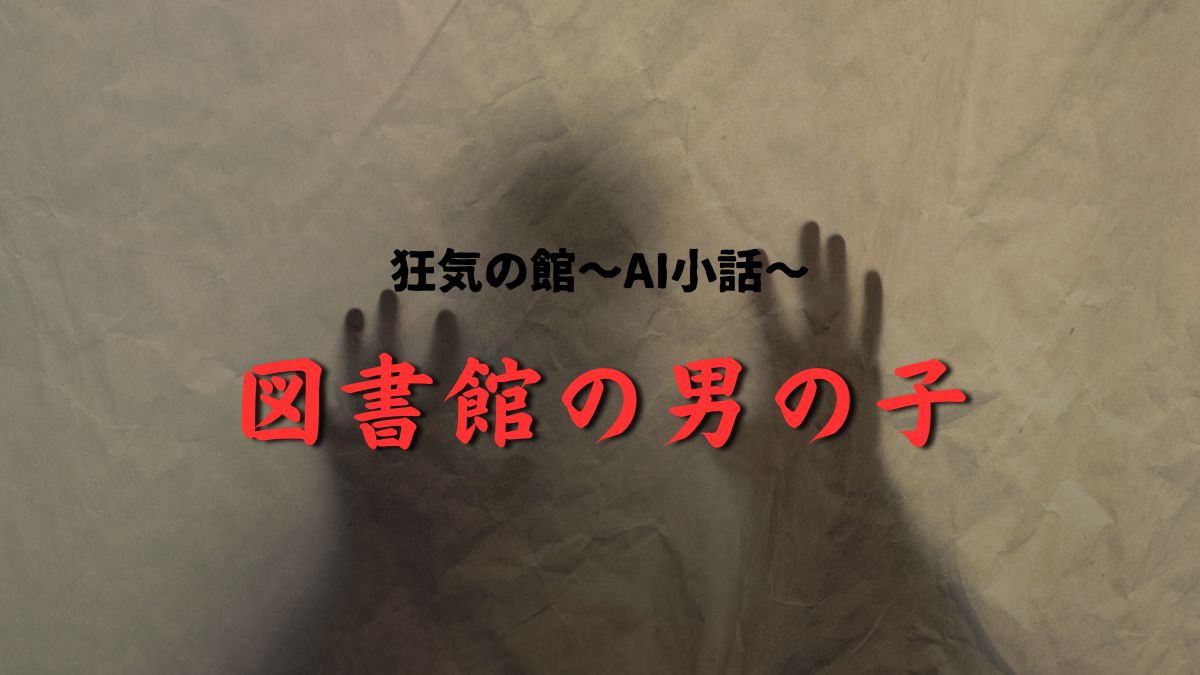


コメント