「この話、なんか引っかかるけど、どこが怖いの?」
読書好きなら一度は体験したことがある、あのゾワッとする感覚。あなたが気づけなかったたった一つの違和感が、日常を崩壊させる。それが「意味が分かると怖い話」の醍醐味です。
当記事は、ネットに溢れる普通の意味怖とは一線を画す、「狂気の館」オリジナルのショートホラーを厳選してお届けします。
明るすぎる娘の笑顔、ベッドの下から聞こえる小さな物音、深夜に響く洗濯機の不気味な音…。
平凡な日常風景に隠された、致命的な「ズレ」。それは人為的な悪意か、超常的な現象か、あるいは自分自身の記憶違いか。そんな「違和感」そのものに焦点を当てた10本の物語を集めました。
すべての物語は、<物語の裏側>と<論理的な真相>をセットで解説しています。
まずはあなたの直感で物語の違和感を見つけ出してみてください。もし分からなければ、下の【解説付き】エリアで、一緒に答え合わせをしましょう。
あなたがこの10話の真相を読み終える頃には、きっと「親切な人の缶コーヒー」や「鏡に映る自分の姿」が、これまでと同じようには見えなくなっているはずです。
さあ、あなたの日常は、本当に「正常」でしょうか?
『意味が分かると怖い話』 まとめ10選 (Vol. 2)

① 完璧な笑顔
妻を亡くして二年。俺は、新しいパートナーの「アスカ」と、娘の「ハナ」との三人で、新しい生活を始めていた。アスカは本当に優しい女性で、心を閉ざしがちだったハナにも、献身的に接してくれた。
「ハナちゃん、こっち向いてー!」
アスカは写真を撮るのが趣味だった。天気の良い休日、庭の古い木製の椅子にハナを座らせ、写真を撮っている。
「そう、いい笑顔! 可愛い!」
アスカが笑うと、ハナも、ぎこちないながら笑顔を返す。その光景が、俺の新しい幸せの象徴だった。
その夜。アスカが撮った写真を、リビングのPCで見ていた。
どれも、ハナが楽しそうに笑っている、素晴らしい写真だ。
「この一枚、最高じゃないか」
俺は、ハナが庭の椅子で笑っているベストショットを拡大した。
…ん?
俺は、その写真に、強烈な違和感を覚えた。
ハナの笑顔が、どこか不自然なのだ。口は笑っているのに、目が、まるで何かに怯えているように、固くこわばっている。
俺は、ハナの目の部分を、さらに拡大した。
(なんだ、これ…)
ハナの瞳が、真昼の屋外だというのに、ありえないほど大きく、真っ黒に見開かれていた。
まるで、暗闇で何か恐ろしいものを見た時のように。
「パパ…?」
不意に、背後からハナの声がした。
振り向くと、ハナが、俺が今見ているPCの画面を、青ざめた顔で凝視していた。
「…ちゃんと、笑えてなかった…?」
ハナは、ガタガタと震えながら、そう呟いた。
「ごめんなさい…ごめんなさい…明日、アスカお母さんともう一回、練習するから…」
俺は、ハナが何を言っているのか、理解できなかった。
「練習」…? 一体、なんの…?
なぜ怖いのか?
一見、新しい母親と娘が、ぎこちないながらも幸せな家族になろうとしている日常の風景。 しかし、違和感は「明るい屋外なのに、異常に散大している娘の瞳孔(恐怖のサイン)」と「娘の“ちゃんと笑えてなかった?”“練習するから”という謎の謝罪」。 真相は、アスカは「優しい母親」などではなかった。彼女は、夫(主人公)がいないところで、娘のハナに「完璧な笑顔」を強要し、日常的に虐待(あるいは恐怖による調教)を行っていた。 ハナの「ぎこちない笑顔」は、恐怖の中で必死に作らされた表情だった。 主人公は、娘が何を「練習」させられているのか、その恐ろしい真実に気づいてしまった。
② 新しいクレヨン
俺たち夫婦は、息子のハルトが子供部屋を欲しがるようになったのを機に、中古の一軒家に引っ越した。
日当たりも良く、ハルトも大喜びで、リビングの棚には新しく買った写真立てに家族三人の笑顔が飾られている。
ただ、一つだけ問題があった。ハルトが、壁や床に落書きをするようになったのだ。
以前のアパートでは、そんなことは一度もしなかったのに。
「ハルト、ダメじゃないか」
「僕じゃないよ! “お友達”がやったの!」
ハルトはそう言って、新しいクレヨンの箱を抱きしめていた。
(空想の友達か…環境が変わって、ストレスが溜まっているのかもしれないな)
俺と妻は、そう結論付けた。
その夜。俺はハルトの部屋で寝かしつけをしていた。
ハルトが眠ったのを確認し、部屋を出ようとした時、ベッドの下から、コトン、と小さな音がした。
(クレヨンでも落ちたか?)
俺は、ベッドの下を覗き込んだ。
暗闇の中、ハルトが持っているのと同じクレヨンの箱が落ちていた。
俺はそれに手を伸ばした。
その時、俺は気づいてしまった。
そのクレヨンの箱が、俺たちがハルトに買い与えた「12色セット」の箱ではなく、
明らかにサイズが大きい、「24色セット」の箱であることに。
そして、その箱の横、暗闇の奥から、小さな子供の手がもう一本現れ、俺が今まさに手に取ろうとしたクレヨンの箱を、サッと引き戻した。
「…それ、わたしの」
女の子のような、かすれた声が、ベッドの下から響いた。
なぜ怖いのか?
一見、引っ越した子供が空想の友達(イマジナリーフレンド)を作り出し、イタズラ(落書き)をしているという、よくある日常の話に見える。 しかし、違和感は「買い与えた覚えのない“24色セット”のクレヨン」が、「“お友達”がいる」とハルトが言っていたベッドの下から出てきたこと。 真相は、ハルトの「お友達」は空想などではなく、その家に以前から棲み着いていた「子供の霊(あるいは何か別の存在)」だった。 「落書き」をしていたのは、その「お友達」本人。 ハルトは、その存在と本当に「一緒に遊んで」おり、親(主人公)にはその姿が見えていなかっただけ。 主人公は、息子の「空想」だと思っていたものが、「実在」する恐怖の存在であった決定的な証拠(=物理的なクレヨン)に、至近距離で遭遇してしまった。
③ ドラムの傷
中古の一軒家に引っ越して一ヶ月。私は、この家の古いドラム式洗濯機が苦手だった。
夫は「まだ使えるんだから」と言うが、回すと「ゴウン、ゴウン」と重い音がするし、何より、なぜか洗面所の隅(脱衣所)ではなく、薄暗い地下室の片隅にポツンと置かれているのが不気味だった。
特に深夜、夫が寝静まった後に洗濯を回すのが嫌だった。
深夜の静寂の中、地下室から響いてくる「ゴウン…ゴウン…」という音に混じって、
「ガリッ…ガリッ…ガリガリッ…」
まるで、誰かが内側から硬いものでドラムを引っ掻くような、甲高い音が聞こえるのだ。
(きっと、服のジッパーか何かが当たってる音よね…)
私はいつも、そう自分に言い聞かせていた。
その夜も、私は深夜に洗濯機を回していた。
案の定、地下室から「ガリガリガリッ!」と、ひときわ大きな音が響く。
直後、運転が止まった。エラー音も鳴らない。ただ、静かになった。
(見に行くしかないか…)
私は恐る恐る、地下室への階段を下りた。
洗濯機は、中途半端な角度で止まっていた。
「もう、なんで…」
私が扉(フタ)を開け、濡れた洗濯物を取り出そうと手を突っ込んだ、その時。
指先に、何か硬いものが触れた。
それは、夫のYシャツに絡みついていた、薄汚れた「爪」だった。
三日月型に欠けた、人間の、親指の爪だった。
全身に悪寒が走った。
(どうして、こんなものが…?)
私は、洗濯機のドラム(内側)を覗き込んだ。
そして、見てしまった。
ステンレス製であるはずのドラムの内壁が、無数の、おびただしい数の「引っ掻き傷」で、白くささくれていたことを。
まるで、内側に閉じ込められた誰かが、外に出ようと必死で…。
なぜ怖いのか?
一見、古い洗濯機の不気味な故障(と、たまたま紛れ込んだ爪)の話に見える。 しかし、違和感は「ドラムの内側に、おびただしい数の引っ掻き傷があった」こと。 真相は、「ガリガリ」という音は、ジッパーの音などではなかった。それは、この家の前の住人(あるいは別の誰か)が、何者かによってあの洗濯機に閉じ込められ、絶命するまで内側から必死で爪を立てて「引っ掻き続けた」音、そのものだった。 主人公が聞いた音は、機械の音ではなく、今もなお繰り返され続けている、その時の「絶望の音(残留思念)」だったのだ。 彼女が見つけた「爪」は、その時の「本物」である。
④ 開かない日記
俺の妹は、事故で記憶の一部を失った。それ以来、彼女は毎晩、小さな鍵付きの日記をつけるようになった。
「お兄ちゃん、これだけは絶対に読まないでね」
そう言って、彼女はその小さな鍵をペンダントにして、首から下げていた。
ある日、妹が珍しく「友達と泊まってくる」と言って家を出た。
俺は、妹の部屋で、ふと机の上に置かれた例の日記帳に目を留めた。
(読まないでと言われると、読みたくなるのが人情だよな…)
俺は罪悪感を覚えつつも、彼女がいない今がチャンスだと思った。
だが、日記には鍵がかかっている。
(鍵は、あいつが持っていってる…)
諦めて部屋を出ようとした時、俺は洗面所の鏡に映った自分の姿を見て、ハッとした。
鏡に映る、洗面台のコップ。その縁に、妹のペンダント(鍵)が、無造作に引っ掛けられている。
「バカなやつ! 鍵を忘れていくなんて!」
俺はほくそ笑み、その鍵を掴んで妹の部屋に戻った。
「さて、秘密の暴露だ」
俺は日記帳の鍵穴に、手に入れた鍵を差し込んだ。カチリ、と音はしたが、日記は開かない。
(あれ? 合わない…?)
もう一度、強く差し込んで回してみる。だが、開かない。
なぜだ? これは、あいつが首から下げていた、唯一の鍵のはずだ。俺は、首を傾げながら、もう一度、洗面所の鏡の前に立った。
コップには、確かにペンダントが引っかかっていた。
俺は、鏡に映る自分の姿を、じっと見つめる。
…あれ?
俺は、いつから、「鏡の中に引っかかっている鍵」を、
「現実の鍵」だと、思い込んでいたんだ…?
なぜ怖いのか?
一見、妹の日記を読もうとする兄の、微笑ましい(?)日常の話に見える。 しかし、違和感は「主人公が“鏡の中”の鍵を、“現実の鍵”として手に取り、それを使おうとした」という、物理的にありえない行動。 真相は、主人公(兄)こそが、記憶障害(あるいは別の精神疾患)を抱えていた。 妹がつけていた日記は、事故で記憶を失った妹のものではなく、日々おかしな言動を繰り返す「兄」の行動を記録するための「観察日記」だった。 「読まないでね」という言葉は、「読んだらお前がショックを受けるから」という妹の優しさ(あるいは防御)だった。 主人公は、鏡の中の虚像と現実の区別がつかなくなり始めている自分の「病状」に、この瞬間、直面してしまった。
⑤ 黒いスタンプ
私は、仕事帰りにスーパーに寄るのが日課だった。
その日も、夕食の買い物を終え、両手に荷物を抱えて地下の薄暗い駐車場へと向かった。私の車は、いつも決まって、一番奥の出口に近い隅に停めている。
「お手伝いしましょうか?」
荷物をトランクに詰め込んでいると、背後から穏やかな声がした。
振り向くと、スーツ姿の優しそうな男性が立っていた。
「あ、いえ、大丈夫です!」
「そうですか。あ、でも、トランク、閉め忘れてますよ」
私が鍵を閉めようと振り返った瞬間、男性は「失礼」と言って、私の車のトランクの扉に手をかけ、バタン、と親切に閉めてくれた。
「ありがとうございます、助かります」
「どういたしまして」
男性はにこやかに笑うと、駐車場を出ていった。
その夜は、ひどい雨が降った。
翌朝。私は仕事に向かうため、再びあの駐車場へと向かった。
昨夜の雨はすっかり上がり、路面は乾いていたが、車のボディには雨粒の跡が汚く残っていた。
(洗車しないとな…)
そう思いながら、トランクにカバンを入れようと、車の後ろに回った。
「え…」
私は、その場に凍りついた。
トランクの、ちょうど中央。昨日、あの親切な男性が手をかけた場所に、べったりとした黒い「手形」が残っていた。
(昨日の雨で、泥でも跳ねた…?)
気味が悪くなり、ハンカチで拭き取ろうと手を伸ばす。
だが、それは泥ではなかった。
手形は、昨夜の雨でも流れ落ちず、完全に乾いていた。
それはまるで、黒いインクか塗料で、意図的に「スタンプ」されたかのように、完璧な五本の指の形と、渦巻く指紋の模様までを、くっきりと残していた。
私は、混乱した。
あの親切な男性は、なぜ、自分の指紋を、わざわざ私の車に残していった…?
なぜ怖いのか?
一見、親切な男性に助けてもらったが、翌日その時の手形が残っていた、という少し気味の悪い話。 しかし、違和感は「雨でも流れ落ちない、インクで押したような完璧な指紋(手形)」が残されていたこと。 真相は、あの男性は「親切な人」などではなく、この駐車場で次の「獲物」を選定していたサイコパス(あるいはカルト信者)。 彼は、主人公を「次のターゲット」としてロックオンした。 彼が残した「指紋」は、ミスではなく、意図的なマーキング(印)。「お前はもう俺のものだ」「次はお前だ」という、彼からの「予告状」だった。 「親切」を装ったのは、ターゲット(主人公)の顔と車を確実に覚えるためのカモフラージュだった。
⑥ 親切な運転手
最悪だった。飲み会が盛り上がりすぎ、気づけば「終電」はとっくに出ていた。おまけに、頼みの綱の「スマホ」は、カバンの中で冷たくなっており、充電が切れていた。家族や友人に連絡する手段もない。財布には数千円。明日は朝一番で大事な会議があるというのに。
「どうしよう……」
冷たい11月の雨が、アスファルトを叩き始めた。駅のロータリーには、あれほどいた「タクシー」が一台もいない。
絶望してうずくまりそうになった、その時だった。一台のタクシーが、路地の向こうからスーッと音もなく近づいてきて、私の目の前で停まった。
「どうぞ、乗ってください」
窓が開くと、人の良さそうな中年の運転手が、穏やかな声で言った。神様に見えた。
「ありがとうございます!」
慌てて乗り込むと、車内は暖房が効いていて、ほっと息が漏れた。
「どちらまで?」
私がアパートの住所を告げると、運転手は一瞬バックミラーで私を見て、「ああ、〇〇町の、あの角のパン屋さんの裏のアパートですね。承知しました」と、やけに具体的に返事をした。
(プロはすごいな、住所だけで分かるんだ)
深く考えず、私はシートに身を沈めた。
「大変でしたね、こんな時間まで。雨も強くなってきましたし」
「いえ、もう本当に助かりました…」
「疲れが出たんでしょう。よかったら、これどうぞ。サービスです」
そう言って、彼は車載の小さな保温庫から、温かい缶コーヒーを差し出してくれた。私は恐縮しながらも、その善意を受け取り、一口飲んだ。疲れた体に、甘いコーヒーが染み渡っていく。
そこからの記憶は、少し曖昧だ。よほど疲れていたのだろう。
気づくと、自宅のアパートの前に着いていた。「お客さん、着きましたよ」という声でハッと目を覚ました。
「すみません、寝てしまって…! おいくらですか?」
慌てて財布を出そうとすると、運転手はバックミラー越しにニッコリと笑った。
「いえいえ、こんな雨の日に頑張っているお嬢さんからは、とても貰えませんよ。今日はサービスです」
「そんな、悪いですよ!」
「いいんです。それじゃ、お気をつけて」
そう言うと、彼は私が降りるのを見届けて、雨の闇に静かに走り去っていった。
(世の中、まだ捨てたもんじゃないな…)
私は温かい気持ちで鍵を開け、部屋に入り、そのままベッドに倒れ込んだ。
翌朝。ひどい倦怠感で目が覚めた。まるで鉛を飲んだかのように体が重い。
そして、私は気づいてしまった。
玄関のタタキから、リビング、そして私が今寝ているベッドのすぐ脇まで、点々と、濡れた泥の「足跡」が続いているのを。昨夜は雨だった。私は確かに玄関で靴を脱いだはずだ。
——その時、私は昨夜の「違和感」をぼんやりと思い出した。
「そういえば、あのタクシー……私が乗り込む前から、なんで『迎車』じゃなくて『賃走(※乗客が乗っているサイン)』の赤いランプが点いてたんだろう?」
なぜ怖いのか?
なぜ「賃走」だったのか? 運転手は、主人公のストーカーだったから。 彼は主人公の生活パターン(飲み会があること、終電の時間、スマホの充電が切らしやすい癖)を把握しており、駅前で「獲物」が助けを求めるのを待ち伏せていた。 彼が「賃走」ランプをつけていたのは、彼にとって「主人公を乗せること」自体が正規の営業ではなく、「主人公を(自分の支配下に置いて)家まで送り届ける」という個人的な「仕事(=賃走)」の最中だったから。 彼が住所の詳細を知っていたのも、コーヒー(睡眠薬入り)をサービスしたのも、すべて計画通り。料金を受け取らなかったのは、金銭が目的ではなく、眠っている主人公をベッドまで「運び」、無防備な姿を眺め、部屋に自分の「足跡」を残すことこそが真の「報酬」だったから。 彼は主人公の家の鍵を、すでに(以前侵入した際に)入手、あるいは複製している可能性が極めて高い。
⑦ ゴミ出しの天使
俺が住む「アパート」は、ゴミ出しのルールが異常に厳しい。分別はもちろん、出す時間も曜日の早朝7時から8時までと決められていた。夜勤もある不規則な仕事の俺にとって、それは拷問に近かった。
そんな俺の窮状を救ってくれたのが、隣に住む201号室の女性だった。「よかったら、私が出しておきますよ」と彼女は微笑んだ。言葉に甘えて、俺は夜のうちに自分のゴミ袋を彼女の部屋の前に置かせてもらうようになった。彼女は毎朝、自分のゴミと一緒に、俺のゴミも「ゴミ箱」(集積所)に出してくれる。本当に天使のような人だ。
ある日、俺は珍しく早朝に目が覚めた。せめて今日くらいは自分で出そうと玄関を開けると、ちょうど彼女が俺のゴミ袋を手に持っているところだった。
「あ、おはようございます。いつもすみません!」
「いえいえ、お気になさらず」
彼女はにこやかに会釈し、アパートの階段を降りていった。俺も後を追ったが、彼女は集積所とは逆の、駐車場の方へ向かっていく。
「あの、そっちじゃ…」
「あ、私、車で出勤なので。ついでに会社の近くの集積所に出してるんです。ここのルール、時間とかうるさいでしょ?」
なるほど、と俺は納得した。
翌日、俺は彼女にお礼の菓子折りを渡した。彼女は「そんな、当然のことですよ」と恐縮していた。
だがその夜、俺は自分の部屋で、ある「違和感」に直面し、凍りついた。
晩酌をしようと冷凍庫を開けた俺は、ストックしてあったはずのロックアイスの袋が、空になっていることに気づいた。そして、キッチンのシンクには、見慣れないプラスチック製の「アイストレー」が一つ、綺麗に洗って伏せてあった。俺はこんなもの買った覚えがない。
——その時、俺は昨日の朝の、彼女の「ある言葉」を鮮明に思い出した。
「あ、昨日は夜勤明けでしたよね? お疲れ様です」
(……俺、昨日が夜勤明けだって、彼女に話したことあったか?)
なぜ怖いのか?
なぜ彼女は主人公が夜勤明けだと知っていたのか? 彼女は、主人公のゴミを集積所に「捨てて」などいなかった。彼女は毎朝、主人公のゴミを自分の部屋に持ち帰り、中身を徹底的に漁っていたのだ。 主人公が捨てたレシート、郵便物、食品のゴミ、そして(不規則な仕事の)シフト表の切れ端などから、彼の生活リズム、好み、人間関係、そして「夜勤で家を空ける日」のパターンを完全に把握していた。 彼女が「車で別の場所に出している」と言ったのは、ゴミ漁りの時間を稼ぐための嘘。 アイストレーは、彼女自身の私物。 彼女は、主人公が夜勤で家を空ける完璧なタイミングを狙い、合鍵を使って部屋に侵入した。 彼女は主人公の冷凍庫の氷を使い(あるいは自分の家の氷を持ってきて)、主人公のグラスで飲み物を飲み、くついでおいた。そして、うっかり自分のアイストレーを洗い、そのまま置いていってしまった。 彼女の「親切」は、主人公の個人情報を抜き取り、生活圏内に侵入するための、最も安全な口実だった。
⑧ 青い粘土
私は行きつけの喫茶店で、一時間ほど読書をして過ごすのが日課だ。マスターとも顔なじみで、いつも奥の窓際の席を用意してくれる。家の「鍵」はシンプルで、キーホルダーなどは何も付けていない。
その日もいつものように読書をし、会計を済ませて店を出た。五分ほど歩いたところで、カバンに家の「鍵」がないことに気づいた。血の気が引いた。いつも入れている内ポケットにない。
慌てて喫茶店に引き返す。「マスター!すみません、鍵、見ませんでしたか?」
マスターは「ああ、やっぱり!」と穏やかな顔でレジから出てきた。
「さっきテーブルを拭いていたら、クッションの『隙間』に落ちてましたよ。危ないところでしたね」
彼はそう言って、私の鍵を差し出した。
「ああ、よかった……! 本当にありがとうございます!」
私はその鍵をひったくるように受け取り、安心して店を出た。
自宅アパートに帰り、ホッとしながら鍵穴に鍵を差し込む。
カチリ、と鍵は問題なく回った。
「よかった、開いた……」
安堵して家に入ろうとした、その時。鍵穴から鍵を抜いた私は、指先に奇妙な「粘り気」を感じた。
見ると、鍵のギザギザした溝の部分に、微かな「青い粘土」のようなものが、ねっとりと付着していた。
——その時、私はマスターが鍵を渡してきた時の「ある行動」を鮮明に思い出した。
彼は鍵を渡す直前、エプロンのポケットの中で一度手をゴソゴソと動かし、何かを拭うような不自然な仕草をしていた。
なぜ怖いのか?
なぜ粘土が付着していたのか? マスターは、主人公が落とした(あるいは席を立った隙に盗んだ)「本物の鍵」を拾った後、主人公が戻ってくるまでの短い間に、バックヤードで合鍵の「型」を取っていた。 彼は鍵用の型取り粘土(=主人公が付着に気づいた青い粘土)に鍵を強く押し付け、正確な型を取った。 彼は慌てて鍵についた粘土を拭き取ったが、主人公が想定より早く戻ってきたため、拭き取りが不十分なまま鍵を返すことになった。(エプロンで手を拭ったのはその証拠) マスターが「クッションの『隙間』」という場所を強調したのは、彼がその型取り作業を行う時間を稼ぐための嘘。 主人公は鍵を取り戻すことはできたが、マスターは今、主人公の家の「合鍵の型」を手にするための「型」を手にしている。
⑨ 三杯目の親切
最近、職場で物忘れがひどい。特に午後になると頭がぼーっとする。大事な会議の日付を間違えたり、取引先の名前を度忘れしたり。「疲れているんだろう」と、上司にも心配されていた。
そんな私を気遣ってくれるのが、隣の席の後輩・A子だ。「先輩、お疲れですよね。これどうぞ」と、彼女は毎日、昼休み明けに必ず温かい「コーヒー」を淹れてくれる。
「いつも悪いね」と恐縮する私に、A子は「いえいえ! あ、先輩は『砂糖』3杯でしたよね? バッチリです!」と人懐っこく笑う。
(あれ? 俺、ブラック派なんだけどな…)
そう思ったが、A子の「親切」を無下にするのも悪く、ここ数ヶ月、彼女が淹れてくれる甘いコーヒーを毎日飲み続けていた。
ある日、A子がインフルエンザで一週間休んだ。
私は仕方なく、久しぶりに自分でブラックコーヒーを淹れた。するとどうだろう。その日は午後になっても全く頭がぼーっとしない。むしろ、ここ数ヶ月なかったほど頭が冴え渡り、仕事が捗った。
そして、休み明け。A子が「ご心配おかけしました! コーヒーどうぞ!」と差し出してきたカップを見て、俺の胸に「ある不安」がよぎった。
A子のデスクの引き出しの奥。いつもは隠れている場所に、彼女がインフルエンザ中に飲んでいたという「風邪薬の瓶」が転がっているのが見えた。
——その瓶のラベルには、『睡眠改善薬(粉末タイプ)』と書かれていた。
その時、俺はふと思い出した。A子はいつも「砂糖3杯ですね!」と言いながら、給湯室から戻った後、俺にコーヒーを渡す直前に、必ず一度自分のデスクの「引き出し」を開け、何かゴソゴソと作業をしていた。
なぜ、砂糖を給湯室で入れてこないんだ……?
なぜ怖いのか?
なぜA子は自席の引き出しで作業したのか? A子は、主人公のパフォーマンスを意図的に下げるため、毎日コーヒーに「睡眠改善薬(睡眠導入剤)」を混ぜていた。 主人公がブラック派であることを知っていながら、あえて「砂糖3杯」と言ったのは、薬の「苦味」をごまかすための口実(あるいは、主人公の注意を「砂糖」に向けさせるためのミスリード)。 主人公がA子の親切を断れない性格であることを見抜き、巧妙に薬を飲ませ続けていた。 主人公の物忘れや倦怠感は、疲労ではなく、薬の副作用だった。 A子が風邪で休んだ日に主人公の頭が冴えたのは、薬が切れたから。 そしてA子のデスクにあった空き瓶は、彼女が風邪薬として使ったのではなく、毎日主人公に飲ませ続けた「睡眠改善薬」の残骸だった。彼女が給湯室ではなく、自席の引き出しで作業していたのは、人目につかないよう、その瓶から薬の粉末をコーヒーに混入させるためだった。
⑩ 午前二時の物音
両親が旅行で家を空け、俺は一週間、実家で一人きりの夜を過ごしていた。実家は古く、夜になるとあちこちで「軋む」音がする。
三日目の「深夜」。午前二時ちょうどだった。階下から「ガタン」と物が落ちる音がした。泥棒かと思ったが、音はそれきりだ。怖くなって朝まで布団に潜っていた。
翌朝、階下のリビングを調べると、本棚から辞書が一冊落ちていただけだった。「古い家だからな」と自分を納得させた。
だが、その夜も、午前二時ちょうど。「ガタン」。
翌日も、午前二時ちょうど。「ガタン」。
それは毎晩続いた。決まって同じ時間に、辞書が一冊だけ落ちるのだ。
五日目の夜。俺は意を決して、午前二時をリビングで待ち構えることにした。息を殺して本棚を見つめる。
時計の針が二時を指した、その瞬間。
「ガタン」
辞書は落ちなかった。音は、俺がいるリビングの「隣の『キッチン』」から聞こえた。
そこには誰もいないはずだ。
恐怖で体が動かない。俺は、ある「違和感」に気づいてしまった。
(待てよ。この家、こんなに「寒かった」か…?)
——そうだ。今、俺の背後、リビングとキッチンを繋ぐドアの隙間から、開けっぱなしの「冷凍庫」の中から吹き出すような、強烈な「冷気」が流れ込んできている。
なぜ怖いのか?
物音の正体と冷気の意味は? この家には、主人公以外の「誰か」が潜んでいた。 「誰か」は、主人公の両親が家を空けるのを知っており、初日から家のどこか(屋根裏や床下など)に隠れていた。 「誰か」は、主人公が寝静まる「深夜二時」に行動を開始し、食料を漁っていた。 初日に聞こえた「ガタン」という音は、本棚の辞書が落ちた音ではなく、「誰か」がキッチンで「冷凍庫」を開け、凍った肉の塊か何かを落とした音だった。 主人公が「辞書が落ちていた」と勘違いしたのは、「誰か」が物音に気づいた主人公を欺くため、翌朝までに「辞書が落ちた」という偽の状況を作り上げたから。 毎晩二時の物音は、主人公を「家の軋む音(または辞書が落ちる音)」だと慣れさせ、油断させるための偽装工作だった。 そして今夜、主人公が待ち構えていることを知らない「誰か」は、いつも通り午前二時に冷凍庫を開けた。 主人公が感じている「冷気」は、今まさに、隣のキッチンで「誰か」が冷凍庫を開けて立っている証拠だった。
意味が分かると怖い話 Vol. 2 まとめ

最後に
いかがでしたか?
親切な運転手が差し出す缶コーヒー、古い洗濯機から聞こえる異音、そして我が子の不自然な笑顔。
それら日常に潜む「違和感」の裏側が、いつの間にか「狂気」と地続きになっていることが、一番恐ろしいことなのかもしれません。
「狂気の館」では、あなたの日常を破壊するようなショートホラーを、今後も量産していきます。
おすすめ記事

【📚 もっと深い狂気が知りたいですか?】
当館では、「忠義が支配に変わる狂気」を描いた【令和版グリム童話シリーズ】や、人気小説の【伏線解説・考察記事】も公開しています。興味のある方はこちら👇
👇グリム童話を令和版にリメイクしてみたシリーズはこちら
👇人気小説の考察記事はこちら
▼ 狂気の原典を読み解く ▼
ちなみに記事を読む前に小説・原作を読むことをおすすめします!





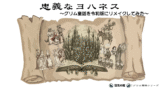



コメント