「この話、なんか引っかかるけど、どこが怖いの?」
読書好きなら一度は体験したことがある、あのゾワッとする感覚。あなたが気づけなかったたった一つの違和感が、日常を崩壊させる。それが「意味が分かると怖い話」の醍醐味です。
当記事は、ネットに溢れる普通の意味怖とは一線を画す、「狂気の館」オリジナルのショートホラーを厳選してお届けします。
親切な隣人の笑顔、毎晩のささやかな祈り、新しく引っ越した夢のマイホーム…。最も安全で安心できるはずの場所が、いつの間にか「誰かの檻」になっている。そんな「人怖」に特化した10本の物語を集めました。
すべての物語は、<物語の裏側>と<論理的な真相>をセットで解説しています。
まずはあなたの直感で物語の違和感を見つけ出してみてください。もし分からなければ、下の【解説付き】エリアで、一緒に答え合わせをしましょう。
あなたがこの10話の真相を読み終える頃には、きっと「隣人の優しさ」や「カレンダーの赤いハート」が、これまでと同じようには見えなくなっているはずです。
さあ、あなたの日常の安全は、どこまで侵食されているでしょうか?
『意味が分かると怖い話』 まとめ10選 (Vol. 3)

1. 親切な隣人
俺は一週間前、アパートの階段で足を滑らせ、左の足首をひどく捻挫した。医者には「全治一ヶ月。絶対安静」と言われ、松葉杖生活を余儀なくされている。そんな俺を、隣人の田中さんが毎日かいがいしく世話してくれていた。彼は俺より少し年上の、人の良さそうな男だ。「お互い様ですよ」と言って、毎日食事を運び、ゴミ出しまでしてくれる。本当にありがたい存在だった。
だが、怪我から一週間が経っても、足首の痛みが一向に引かない。それどころか、ズキズキとした鈍痛が、日に日に強まっている気がするのだ。医者にもらった痛み止めも、ほとんど効かない。そのことを田中さんに相談すると、彼は「そうですか…それは心配だ」と眉をひそめた。「あ、そうだ。僕、マッサージが得意なんですよ。血行を良くすれば、治りも早まるかもしれません。よければ今夜にでも」俺は彼の親切に甘えることにした。
その夜、田中さんが部屋にやってきた。「じゃあ、失礼しますね」彼は俺の左足首を掴むと、ゆっくりと揉み始めた。しかし、その手つきは素人のマッサージとは程遠かった。指が的確に腱と骨の隙間に入り込み、痛みの芯を直接えぐってくる。「いっ…! 田中さん、痛い、痛いです!」俺は悲鳴を上げた。だが、田中さんは笑顔のまま、力を緩めない。
「あ、すみません。でも、ここが凝ってるんですよ」彼は笑顔でそう言うと、さらに指に力を込めた。ゴリッ、と骨がきしむような嫌な音が響く。俺は激痛で身をよじった。「やめ…やめてくれ!」「ダメですよ、安静にしてないと」田中さんは困ったように笑いながら、俺の足首を掴む手を離さない。その時、俺はふと思い出した。彼が俺の部屋に入ってくるとき、いつも薄い壁一枚を隔てた彼の部屋から、微かに酸っぱいような異臭が漏れていたことを。そして、一週間前に俺が階段から落ちたあの日。彼が真っ先に駆けつけ、俺の足首を「応急処置」してくれた時の、あの異常に手際の良い手つきを。痛みと混乱の中、俺は親切な隣人の笑顔を、ただ見つめることしかできなかった。
なぜ怖いのか?
一週間経っても足の痛みが引かないのは、隣人が主人公を「監禁・飼育」する目的で、食事に薬物を混ぜ、毎晩のマッサージと称して意図的に足首の腱や骨を破壊し続けているからです。階段落ちも事故ではなく、隣人が仕組んだもの。手際の良すぎる応急処置や、壁の向こうの異臭は、その加害行為の証拠でした。
2. 井戸の神様
見知らぬ土地での一人旅は、私の悪い癖だった。案の定、ガイドブックにも載っていない山道を散策しているうちに、完全に道に迷ってしまった。時刻はもう夕方。オレンジ色の光が木々の隙間から差し込み、急速に気温が下がっていくのが分かる。スマホはとっくに圏外だ。途方に暮れて泣きそうになった時、畑仕事帰りらしい、人の良さそうなおばあさんに出会った。「あらあら、お嬢さんどうしたの? 道に迷った? まあ、この時間からじゃバスもないし、麓まで歩くのは無理だよ」
「今夜はうちに泊まっていきなさい。何もないところだけどね」おばあさんの善意に、私は心から感謝した。おばあさんの家に向かう細いあぜ道に、苔むした古い井戸があった。「昔はね、この井戸がここの神様だったんだよ。今はもう誰も拝まないけどね」おばあさんはそう言って、一瞬だけ井戸に向かって静かに手を合わせた。家に着くと、おばあさんは温かいお風呂と、山菜の煮物や手作りの漬物といった素朴だが美味しい夕食を出してくれた。「本当にありがとうございます。助かりました」「いいのよ。困った時はお互い様だからね」私はすっかり安心して、疲れもあってすぐに眠気が襲ってきた。
「明日の朝、一番のバスが出る時間に合わせて、車でバス停まで送ってあげるから。ゆっくりおやすみ」おばあさんの優しい声に送られ、私は客間のふかふかの布団にもぐりこんだ。しかし、夜中。ふと、突き刺すような悪寒で目が覚めた。おかしい。部屋はストーブが焚かれていて暖かいはずなのに、体の芯が凍えるように寒い。喉が渇いたので水を飲もうと起き上がると、廊下を隔てたおばあさんの部屋から、話し声が聞こえてきた。
こんな深夜に、誰かと電話だろうか。「ええ、ええ…本当に助かりました。今度の子はとても素直で、手がかからなくて…」楽しそうな、弾んだ声。「はい、もちろん。明日も、ちゃんとご挨拶させますから」私は違和感を覚えた。おばあさんの家は、電話回線を引いているようには見えなかった。そっと襖を数センチだけ開け、廊下の先を覗き見る。おばあさんは、電話など持っていなかった。彼女は玄関の土間に立ち、外に向かって――そう、あの古い井戸の方向に向かって、嬉しそうに一人で話し続けていた。そして、私は見てしまった。おばあさんの背後、居間の壁に並んでかけられた、いくつものカレンダーを。それはすべて、去年の日付――2024年のまま、一枚も破られていなかった。
なぜ怖いのか?
「去年の日付のままのカレンダー」が何枚もかかっていたことが決定的な違和感です。主人公は道に迷った最初の日を毎日繰り返させられている状態で、すでに一年以上監禁されています。おばあさんの優しい言葉は、井戸の神様(あるいは別の存在)への「生贄」を逃げさせないための、毎日繰り返される嘘なのです。
3. 愛しすぎたから
私と親友のミカは、中学の生物委員だった。顧問の鈴木先生はいつも穏やかで、私たちが飼育している動物たちのことを一番に考えてくれる、生徒からも人気の先生だった。特にミカは、先生の影響もあってか、極端なほどの動物好きだった。裏庭のニワトリ小屋にいるニワトリ一羽一羽に名前をつけ、まるで我が子のように可愛がっていた。先生も「ミカさんは本当に優しいね」と、いつも目を細めて彼女を見ていた。
異変が起きたのは、先週からだ。ニワトリ小屋のニワトリが、二日と空けずに一羽、また一羽と、姿を消し始めたのだ。「きっと、イタチかキツネが入る隙間があるんだ…」先生は金網を補強し、罠を仕掛けたが、効果はなかった。ミカはそのたびにひどく落ち込み、日に日に元気がなくなっていった。餌やりの時も、空になった止まり木を見ては泣き出しそうになる。「ミカ、大丈夫…?」「大丈夫じゃないよ…! 私が、もっとちゃんと守ってあげてれば…」そんな彼女を、先生はいつも隣で優しく慰めていた。
その日の放課後。当番だった私とミカがニワトリ小屋の掃除を終えると、ミカが言った。「ごめん、私ちょっと先生に用事があるから。先に帰ってて」私は頷き、一人で校門を出た。だが、通学カバンに筆箱を入れ忘れたことに気づき、急いで教室へ引き返した。もう誰もいないはずの校舎は静まり返っていた。教室で筆箱を見つけ、急いで帰ろうと昇降口に向かった時、裏庭のニワトリ小屋の方から、物音が聞こえた。(イタチ!?)私は息を殺し、音を立てないように、そっとニワトリ小屋の裏手に回った。
そして、私は見てしまった。ミカが、小屋の中で、死んだニワトリを抱きしめていた。彼女は泣いていた。「ごめんね…ごめんね、ココちゃん…。寒かったよね、苦しかったよね…」そう呟きながら、彼女は持っていたスコップの角で、すでに動かないニワトリの首を、何度も何度も突いていた。私は声も出せず、その場で凍りついた。その時、背後の物置の影から、鈴木先生が静かに出てきた。「ああ、見てしまったか」先生は、泣いているミカを見るのと同じ、あの優しい目で私を見た。「シー。ミカは、ああしないと落ち着けないんだ。あの子は動物を愛しすぎているからね。可哀想な動物を、楽にしてあげてるだけなんだよ」私は先生の言葉の意味が理解できず、ただ震えていた。先生が「教室に戻ろうか」と私の肩に手を置く。その瞬間、先生の手首から、ミカがいつもつけている甘ったるいバニラの香水の匂いが、強く漂ってきたことに気づいてしまった。
なぜ怖いのか?
先生の「手首から親友と同じ香水の匂い」がしたことが決定的な証拠。親友ミカは「動物愛護の歪み」からニワトリを殺害しており、先生はその異常性を「優しいことだ」と肯定し、共犯関係を結んでいます。主人公は、その異常な共犯者二人による「秘密の殺害儀式」の現場に足を踏み入れてしまいました。
4. 揃えられた靴
私は都内で一人暮らしをしている。今日は残業で終電間際、くたくたになってアパートの自室にたどり着いた。重い玄関のドアを開け、鍵をかける。真っ暗な部屋に「ただいま」と呟き、ハイヒールを脱ぎ捨てた。早くシャワーを浴びて眠りたい。
リビングのドアを開けると、冷えた空気が流れ出てきた。エアコンはつけていないはずなのに、妙にひんやりとしている。(窓、開けっ放しだったかな…)そう思い、リビングを横切ってベランダの窓を確認しにいく。鍵は、ちゃんと閉まっていた。気のせいか、と室内の電気をつける。その時だった。「……ん……ふふん……」微かに、本当に微かに、鼻歌のようなものが聞こえた。私は心臓が跳ねるのを感じた。音は、キッチンの奥、備え付けのパントリー(食品庫)のあたりから聞こえる。
全身に悪寒が走った。(誰か、いる)強盗? ストーカー?私は息を殺し、音を立てないよう、ゆっくりと玄関に向かって後ずさった。パントリーの扉が、数センチだけ開いている。その暗い隙間の向こうに、何かがいる。私が玄関のたたきに片足を下ろした、その瞬間。「……ふふん……」鼻歌がピタリと止んだ。そして、パントリーの扉の隙間から、暗闇に慣れた二つの目が、こちらをじっと見ていることに気づいてしまった。
私は声にならない悲鳴を上げ、ドアノブに手をかけた。「ひっ…!」早く、早く外に!パニックになりながら、脱ぎ捨てたはずの自分の靴(ハイヒール)を履こうと、玄関のたたきに目を落とした。そして、私は凍りついた。そこには、確かに私のハイヒールがあった。だが、その真横に、まるで最初からそこにあったかのように。一足の、泥で薄汚れた、見覚えのないスニーカーが、きちんと踵を揃えて、まっすぐドアの方を向いて、置かれていた。あれ? なんで? 私は、いつ、あんな靴を…?私のハイヒールと、ぴったり並んで…。背後で、パントリーの扉が、ギィ…とゆっくり開く音がした。
なぜ怖いのか?
侵入者が、逃げる気もなく、主人公のハイヒールの横に「泥で汚れたスニーカー」をきちんと踵を揃えて置くのは不自然です。その「誰か」は、パントリーや屋根裏で長期間潜伏生活を送る「寄生者(住人)」であり、そこを「自分の家」として認識しているからです。主人公は、ただの「帰宅」と鉢合わせてしまっただけなのです。
5. 黒い瞳のともだち
私の妹・ハナは、家の裏にある廃線の線路で遊ぶのが大好きだった。危ないから行っちゃダメだと叱っても、「大丈夫! ともだちと遊んでるだけだもん!」と、いつもこっそり抜け出してしまう。その「ともだち」とやらは、私や両親の前には一度も姿を見せたことがない。
その日も、夕飯の時間になってもハナが帰ってこない。私はため息をつきながら、いつもの線路まで迎えに行った。ハナは、線路脇の草むらにしゃがみ込み、何かと楽しそうにおしゃべりをしていた。「ハナ! 帰るよ!」声をかけると、ハナは「あ、お姉ちゃん!」と振り向いた。「今ね、ともだちとかくれんぼしてるの」「もう暗いから終わり。ほら、行くよ」私がハナの手を引いて歩き出す。その時、すれ違うように、線路脇の暗い用水路の中から、カサリ、と音がした。
(気のせいか…)私は足を止め、用水路の暗がりに目を凝らした。一瞬、そこに小さな女の子がうずくまっているのが見えた気がした。その顔は泥で汚れ、異様なほど大きな黒目で、じっとこちらを見つめていた。「……!」私が息を呑むと、その姿はフッと消えた。
家に帰り、ハナを叱ると、彼女は「ともだちが、お姉ちゃんのことキライだって」と呟いて、自分の部屋に閉じこもってしまった。その夜中。私は、隣の部屋で寝ているハナの部屋から、物音がするのに気づいた。(また寝ぼけてるのかな…)そっとドアを開けると、ハナはベッドの上でぐっすり眠っていた。ホッとして部屋を出ようとした時、床に落ちていたハナの人形が目に入った。ハナが毎晩一緒に寝ている、一番お気に入りのウサギの人形だ。私はそれを拾い上げ、ベッドに戻してあげようとした。そして、全身に鳥肌が立った。ウサギの人形の首が、ありえない方向にグニャリと捻じ曲げられていた。そして、その顔。両方の目の部分が、黒いマジックで、何度も何度も塗りつ潰されていた。ハナは、マジックでイタズラをするような子じゃない。じゃあ、一体、誰が…?
なぜ怖いのか?
妹ハナの「ともだち」は空想ではなく、線路脇の用水路に潜む実在の存在です。姉が目撃した「黒い瞳の女の子」がそれであり、「姉が邪魔者」だと認識しました。人形の首を捻じ曲げ、目を黒く塗りつぶしたのは、その存在がすでにハナの部屋に侵入し、姉への警告として人形を破壊したことを示しています。
6. 償いの痣
ひどく疲れていた。上司との些細な口論をいつまでも引きずってしまい、自己嫌悪で頭が重い。深夜、車を走らせる人気のない国道は、まるで自分だけが世界から取り残されたような気分にさせた。「はぁ…なんか、罰でも当たったみたいだ」重い溜息と共に、そう独りごちた。
ぼんやりとした意識の中、前方に歩道橋の暗い影が見えてくる。その、真下を通過しようとした、まさにその瞬間。黒い影が、視界の端で、歩道橋の上から落ちるのが見えた。「えっ」ブレーキを踏む時間もなかった。
ドンッ、という鈍い衝撃音。だが、それは想像していたよりもずっと軽かった。「うわっ!」ハンドルは取られなかった。恐る恐るバックミラーを覗き込む。だが、国道のアスファルトには何も見えない。(今の、何だ…? カラス? それとも、誰かがゴミでも落としたのか?)心臓が激しく鳴っていたが、車を停めて確認する勇気はなかった。「…ゴミだ。きっと、大きなゴミ袋か何かだ」私は自分にそう言い聞かせ、アクセルを踏み込んだ。
アパートに帰り着き、震える手で鍵を開ける。シャワーを浴びようと服を脱いだ時、鏡に映った自分の体を見て、息を呑んだ。左の肩から鎖骨にかけて、くっきりと紫色の痣が浮かび上がっていた。(ああ…シートベルトか。あの時、そんなに強くブレーキ踏んでたんだ、私…)ホッと安堵したのも束の間、私はその痣から目が離せなくなった。それは、シートベルトの線が作るような、一本の直線的な痣ではなかった。まるで、小さな子どもが必死にしがみついてきたかのように。五本の指の形が、くっきりと、私の鎖骨に刻まれていた。私は、混乱したまま、その痣をただ見つめることしかできなかった。
なぜ怖いのか?
主人公の鎖骨に刻まれた痣が、シートベルト痕ではなく、小さな子どもの「五本の指の形」をしていたことが真実です。主人公は歩道橋から落ちてきた子どもを撥ねたという事実から目をそらすため、無意識に記憶を「ゴミを撥ねた」とすり替えたのです。霊(怨念)が「罰」として、主人公の体にしがみついた痕跡であり、一生その罪から逃れられないことを暗示しています。
7. 歪んだ献身
俺の妻・ミキは、二週間前に自宅のベランダで足を滑らせ、運悪く額を強く打ってしまった。それ以来、彼女はベッドの上でぼんやりと過ごすことが多くなった。「ミキ、大丈夫か? 今日は天気がいいぞ」声をかけても、彼女は焦点の合わない目でこちらを見るだけで、時折、喉の奥で小さく唸るだけだ。
医者は「脳への衝撃は軽微だが、精神的なショックが大きいのだろう」と言っていた。俺は会社に長期休暇を申請し、ミキの看病に専念することにした。俺が驚かせたせいで彼女は転んだのだ。俺が一生、彼女を守らなければならない。「ほら、ミキ。お粥作ったぞ。あーん」俺は毎日、三食すべてを手作りし、彼女の口元へ運んでやった。彼女が拒否しても、俺は「食べないと元気にならないだろ?」と優しく諭し、時間をかけて食べさせた。
今日、久しぶりに義母(ミキの母)が見舞いに来た。義母は、痩せて生気を失ったミキの姿を見て、俺を睨みつけた。「あなた…本当に、ミキは自分で転んだの? この子の額の傷…転んだだけにしては、酷すぎない…?」「何言ってるんですか、お義母さん! 僕はミキを献身的に看病してるんですよ!」俺が声を荒らげると、義母は「ごめんなさい…」と怯えたように目を伏せ、すぐに帰ってしまった。ひどい言いがかりだ。
義母が帰った後、俺はミキのベッドの横に座った。「ひどいよな、ミキ。俺が、お前を傷つけるわけないのにな」俺はミキの冷たい頬を優しく撫でた。その時、ミキが(いつもは虚ろな目で俺を見るだけなのに)、ビクッと全身を強張らせ、恐怖に引きつった顔で俺の手から逃れようとした。俺は、その反応を見て、無性に腹が立った。(なんで、俺の優しさが分からないんだ?)イライラしながら部屋の窓に目をやると、窓ガラスに映った俺の顔が、怒りのせいで奇妙に歪み、口角が吊り上がっているように見えた。俺は、ふと思い出した。二週間前、ベランダで。俺が「なんで俺の言う通りにしないんだ!」と彼女を突き飛ばした時のことを。彼女が倒れ、額から血を流しても、まだ俺を「化け物を見るような目」で睨みつけてきた時のことを。だから俺は、彼女が「良い子」になるまで、何度も…。
なぜ怖いのか?
義母の「転んだだけにしては酷すぎる傷」という所見と、妻が夫の手にだけ異常な恐怖反応を示したことです。妻が寝たきりなのは事故ではなく、夫(主人公)による日常的な暴力(DV)が原因。夫は、自分の加害行為を「献身的な看病」という優しい記憶にすり替え、妻を完全に支配(監禁・飼育)し続けている「信頼できない語り手」なのです。
8. 黒髪の祈り
私が女手一つで娘を育てるこの古い団地は、家賃が安い分、あちこちが軋む。特に気になるのが、夜中に聞こえる床下からの「コツ…コツ…」という乾いた音だ。管理人に言っても「古いからねえ」と笑われるだけだった。
私の一番の宝物は、娘のリン。特に、床に届きそうなほど長く美しい黒髪は、私の自慢だった。私は毎晩、リンが眠る前に、その黒髪を丁寧に、心を込めて梳かしてやるのが日課だった。そして、リンが寝付くと、枕元でそっと手を合わせる。(この子が、ずっと健やかでいられますように…)それが、私の毎晩のささやかな祈りだった。
その夜も、私はリンの髪を梳かしていた。床下で、また「コツ…コツ…」と音が鳴っている。(またか…)私が顔をしかめると、リンが鏡越しに私を見て、無邪気に言った。「あ、また“コツコツさん”だ」「…リン、知ってるの?」「うん。いつも、お母さんが私の髪を梳かしてくれる時に、嬉しそうにしてるの」私は、梳かす手を止めた。
「…嬉しそうって、どういうこと?」「あのね、床の隙間から、いっつも“コツコツさん”が私のこと見てるの。それでね、お母さんがお祈りしてるとき、いつもこう言うんだよ」リンは、鏡の前で、自分の喉を指差しながら、甲高い声色で真似てみせた。「『はやく、その“かみ”を、よこせ』って」私は、手に持っていた櫛を落とした。混乱する頭で、必死に記憶をたどる。先週、リンの部屋の畳を掃除した時、畳の隙間に詰まっていた、あの大量の見覚えのない「泥」と「抜け毛」のことを。
なぜ怖いのか?
娘リンが「コツコツさん」の言葉(『はやく、その“かみ”を、よこせ』)を知っていたことです。「コツコツさん」はネズミではなく、床下に潜む人間で、リンの髪に執着していました。畳の隙間にあった「泥と抜け毛」は、その存在がすでに一度、リンの部屋に侵入していたことを示唆しており、母親が「祈っている」間も、娘の髪は狙われ続けていました。
9. 新しい家族
俺たち家族4人は、夢だったマイホーム(中古)に引っ越した。少し古いが、広い庭と、何より大きな地下室があるのが決め手だった。「パパ、ここ秘密基地みたい!」幼い息子と娘は、初めて見る地下室に大はしゃぎだった。
引っ越して数日後、俺は地下室の隅に、古いアルバムが置かれているのを見つけた。前の住人の忘れ物だろう。中には、俺たち家族が越してくる前に住んでいたであろう、見知らぬ家族の写真がびっしりと貼られていた。夫婦と、幼い兄妹。…まるで、俺たち家族の構成とそっくりだった。写真の中の彼らは、皆、幸せそうに笑っていた。
そのアルバムをリビングに持って上がると、妻が「まあ、素敵ね」と微笑んだ。「なんだか、私たちみたいね」妻は、そのアルバムを、俺たち自身の家族写真が飾られた棚に、並べて置いた。その日の午後。俺は庭で荷解きをしていた。ふと家の方を見ると、地下室の小窓(地面スレスレにある窓)が開いており、息子のタクヤが、そこから俺に向かって「パパ!」と手招きをしているのが見えた。「おい、危ないぞ! すぐ上がるから待ってろ!」俺は慌てて家の中に入った。
だが、俺がリビングを通り抜けて地下室への階段を降りると、タクヤの姿はどこにもなかった。「タクヤ? どこだ?」地下室は、がらんとして静まり返っている。「パパ、なにしてるの?」声がして振り返ると、タクヤは、地下室の「入り口の階段の上」に立って、俺を不思議そうに見下ろしていた。俺は、全身に悪寒が走った。じゃあ、さっき俺が庭から見た、あの地下室の小窓から俺に手招きをしていた「タクヤ」は、一体、誰なんだ…?俺は、リビングの棚に並べられた、二つのアルバムを思い出した。
なぜ怖いのか?
「庭で見た地下室の小窓にいるタクヤ」と、「実際は階段の上にいたタクヤ」という、物理的な位置の矛盾です。主人公が目撃したのは、前の住人の「息子(霊)」であり、その一家は地下室で不幸な目に遭い、成仏できていません。彼らは、自分たちとそっくりな構成の新しい家族(主人公一家)を、自分たちの「代わり」として地下室に引きずり込もうと、「手招き」を始めたのです。
10. 優しい記憶
俺の妻は、最近少し、物忘れがひどくなった。「あなた、今日って何日だっけ?」「今日は土曜日だよ。さっきも言っただろ?」「ごめんなさい…」医者は、ストレスによる一時的なものだろう、と言うだけだった。俺は、妻が不安にならないよう、優しく接することを心掛けていた。
俺は、妻のために、大きなカレンダーをリビングにかけ、その日の予定を太いマジックで書き込むようにした。「ああ、ありがとう。助かるわ」妻は嬉しそうに笑った。それでも、彼女は忘れてしまう。俺は、キッチンの壁に「今日は燃えるゴミの日」と書いたメモを貼った。
その日の夜。俺が仕事から帰ると、キッチンには朝出したはずのゴミ袋が、そのまま置かれていた。「…ミキ、ゴミ出すの、忘れたのか?」「え…? あ…ごめんなさい、私…」まただ。俺はため息をついた。「壁にメモ、貼っておいただろ?」「メモ…?」妻はキョトンとした顔で壁を見た。俺が今朝貼ったはずのメモが、なくなっていた。
(風で落ちたのか?)俺は仕方なく、キッチンのゴミ箱を漁った。生ゴミに混じって、何か紙くずが手に触れた。それは、俺が今朝書いた「今日は燃えるゴミの日」のメモだった。くしゃくしゃに丸められて、捨てられていた。俺は、混乱した。妻は「忘れた」のではない。「意図的に捨てた」…?なぜ?その時、俺はリビングのカレンダーに、見覚えのない印が付けられていることに気づいた。俺が「出張」と書いた日の横にだけ、小さな、赤いハートマークが、繰り返し、繰り返し、びっしりと書き込まれていた。
なぜ怖いのか?
妻が「忘れた」のではなく、夫の貼ったメモを「意図的にゴミ箱に捨てていた」こと、そして夫の出張日にだけ赤いハートマークを付けていたことです。妻は物忘れではなく、夫(主人公)の「親切(メモやカレンダー)」を「支配と監視」と認識し、唯一夫がいない日を「安全で幸福な日」としていたのです。夫は、自分が加害者であるという狂気に気づいていないまま、妻を追い詰めていました。
最後に

いかがでしたか? 鏡に映る自分の顔、隣人の優しい笑顔、そして家族の安らぎ。それら日常の裏側が、いつの間にか「誰かの狂気」の上に成り立っていることが、一番恐ろしいことなのかもしれません。「狂気の館」では、あなたの日常を破壊するようなショートホラーを、今後も量産していきます。
おすすめ記事
【📚 もっと深い狂気が知りたいですか?】
当館では、「忠義が支配に変わる狂気」を描いた【令和版グリム童話シリーズ】や、人気小説の【伏線解説・考察記事】も公開しています。興味のある方はこちら👇
👇グリム童話を令和版にリメイクしてみたシリーズはこちら
👇人気小説の考察記事はこちら
▼ 狂気の原典を読み解く ▼
ちなみに記事を読む前に小説・原作を読むことをおすすめします!





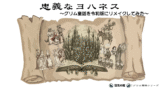



コメント